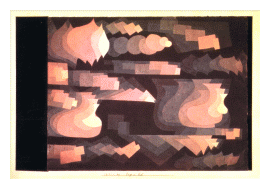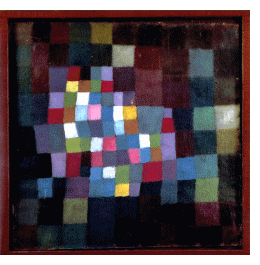ケルステン氏 DR.WOLFGANG KERSTEN 講演会
時間はいずれも予定です
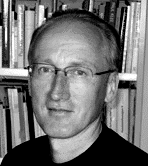 ●9月20日(土) 1時30分
●9月20日(土) 1時30分
傷つけた自己への問い ― 1889年1月、アルルでのゴッホ
会場:学習院大学 主催:学習院大学哲学科/学習院大学文学会
●9月23日(火・祝) 2時
花開く抽象 ― パウル・クレーの反復の芸術
会場:東京国立近代美術館 主催:東京国立近代美術館/日本パウル・クレー協会
●9月27日(土) 1時30分
パウル・クレー ― 自己管理された「傑作」
会場:学習院大学 主催:学習院大学哲学科/美術史学会
●10月5日(日) 10時
パウル・クレー ― 自己管理された「傑作」
会場:京都国立近代美術館
●10月5日(日) 4時15分
傷つけた自己への問い ― 1889年1月、アルルでのゴッホ
会場:法然院
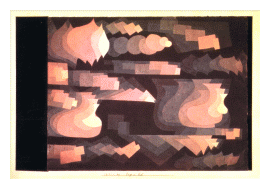
パウル・クレー ― 自己管理された「傑作」
Paul Klee - Die Meisterwerke
Selbstverwaltung statt Fremdverwertung
9月27日(土) 学習院大学
10月5日(日) 京都国立近代美術館
美術における「傑作」というものは、一般の意見、美術批評的な判断、美術史的な評価などが絡み合った、
歴史的な価値評価プロセスの結果として決まってくる。その際、芸術家自身による評価には副次的な役割し
か与えられない。そのような状況に対して、パウル・クレーは、自らの作品の中でどれが傑作であるかを、
自分のみで判断して決めたのであった。そのような事実は、クレー研究の中では夙に知られていたのである
が、クレーが自ら定めた傑作を完全に突き止め、学術的に調査しようという試みは、これまでなされてこな
かった。本講演では、そうした調査研究はどのように構想されるべきか、その結果、どのような美術史的知
見が得られるかということが、一方では作品の体系的な概観を通して、他方では幾つかの選ばれた作例によ
って、明らかにされるだろう。
クレーは、遅くとも1925年以降、紙に彩色した作品と油彩画を1901年制作のものまで遡り、質、寸法、重要
度に従って8つの価格等級に分類したが、その上に最上カテゴリーとして「特別級」(Sonderklasse)を置い
た。そして、その最上カテゴリーの作品は、傑作としての扱いを受け、作品の自己管理という方針に従って、
他人の手には渡されなかった。クレーは、それらの作品を非売品として自分の為にとって置いたのである。
そうした作品として、260点もの傑作が、疑いないものとして確認されているが、それらを完全に突き止める
ことによって、クレーの選択の基準であるとか、手元に取り置かれた傑作の役割といった、根本的に重要な
意味を持つ問いが浮かび上がってくるだろう。
「特別級」カテゴリーの初期作品の例としては、1901年の《浮遊する貴婦人(ポンペイ様式)》と1921年の
《赤のフーガ》が挙げられる。両作品を通して、現在のクレー研究における極めて重要な美術史的な問題の
ひとつが議論されることになるだろう。すなわち、クレーの美術創作と著述における、さらには自筆作品目
録の記帳における、多層的なクロノロジーという問題である。
頁頭へ
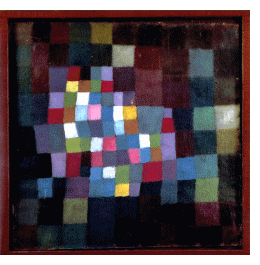
花開く抽象 ― パウル・クレーの反復の芸術
Blühende Abstraktion
Paul Klees Kunst der Reprise
9月23日(火・祝) 東京国立近代美術館
1925年、パウル・クレーは、完全に抽象的な1点の色面コンポジションを描いた。しかし、彼がこの作品の
裏面に書き込んだ題名は、「花開く木」という具象的なものであった。それから9年後の1934年、クレーは
同じく完全に抽象的な色面コンポジションを制作し、これに「開花」という題名を与えた。この2点の油彩
画は、形態、色彩、構成において大変似通っており、そのことから、1934年の作品は、明確な意識をもって
構想された反復であると考えられる。
1925年の《花開く木》は、1994年以来、東京国立近代美術館に所蔵されている。他方、1934年の反復作品《
開花》は、1974年にヴィンタートゥア美術館に寄贈されたチューリヒのある重要な個人コレクションに含ま
れていたものであり、近年では、国際的に著名な建築家レンツォ・ピアノがベルンのクレー・センターを設
計した際のインスピレーション源ともなっている。
これまでのクレー研究の中で、この2作品はしばしば言及されてきたが、その分析は、たいていの場合、正
確ではなく、説得力を持っていなかった。クレー自身は、開花という自然界の成長プロセスとのアナロジー
において自らの芸術創造が理解されることを望んだのであるが、具象的な題名のせいで、研究者たちの間に
は、この2点の作品を巡る余りにも気ままな空想が花開いたのであった。
こうした事情から、この講演では、まず、クレー研究文献にどのような誤りが広がっているかを確認するこ
とから始めたい。そののち、技法面と心理面における厳密な把握を通して、両作品を徹底的に考察する。そ
の考察の結果が美術史的にどのように評価されるかについては、さらに、作品総体の中に組み込まれた生成
・受容の過程が考慮されねばならない。そのような方法により、初めて、東京の絵とヴィンタートゥアの絵
の関連が明らかになる。
最後に、クレーの反復の芸術がどのようなものであるかを知ることによって、両作品のもつアクチュアルな
意味が理解されるであろう。少なくともヴィンタートゥアの作品の場合、そのアクチュアルな意味は、現代
美術と市民的教養との融合から生じているのである。
頁頭へ
傷つけた自己への問い ― 1889年1月、アルルでのゴッホ
Selbstbefragung nach der Selbstverstümmelung
Vincent van Gogh, Arles, Januar 1889
9月20日(土) 学習院大学
10月5日(土) 法然院


アルルの黄色い家でのフィンセント・ファン・ゴッホとポール・ゴーギャンの短期間の共同生活が、1888年
12月23日、ゴッホの精神的な混乱と自らの左耳を傷つけるという行為によって終わりを告げたことは、よく
知られている。収容された病院から退院して10日経った、1889年1月17日、彼は弟のテオに宛てた手紙で、
次のように報告している――「僕はふたたび仕事を始め、アトリエですでに3点の習作を描いた」。
そこで触れられている「3点の習作」のうち1点が《耳に包帯をしてパイプをふかす自画像》(チューリヒ・
クンストハウス寄託)であることは、かなり確実であると考えられる。この油彩画には、対になる作品として、
もう1点の《耳に包帯をした自画像》(ロンドン、コートールド・インスティテュート所蔵)があるが、この
両作品は、1901年3月にパリのベルネム・ジュヌ画廊で開かれた回顧展以来、ゴッホに関するさまざまな書
物の中で、彼の生涯と作品の神話化のために利用されてきたのであった。
ゴッホをめぐる伝説の形成に関しては、近年、その背景を批判的に探る試みが数多く行なわれ、研究が積み
重ねられてきたものの、チューリヒの自画像に関しても、ロンドンの自画像に関しても、入念な考察はなさ
れていない。
作品対象の徹底した分析が、もはや「芸術の自律的な存在」を擁護し得ない、という今日の美術史研究の状
況の中で、一次文献資料と二次文献資料の双方を視野に入れた個別作品研究は、どのように考えられるべき
であろうか? ゴッホの自画像制作における創造行為は、物としての作品の確認と画面の構造の分析という
枠組の中で、いかにして、学問的に再構成されるであろうか? どのような道のりを経て、一方の作品はロ
ンドンに、他方の作品はチューリヒに達したのであろうか? チューリヒの作品とロンドンの作品との間に
は、どのような関係があるだろうか?
そのような問いの全てが、この講演の中で検討され、総体としての作品生成の履歴(integrale Arbeitsbiografie)
という概念に基づいて、その答が提示されることになる。そのような考察によって明らかになるのは、1889
年1月のゴッホにとって重要だったのは、自己の様式化ではなく、むしろ、絵画という媒体を通しての自己
への問いであった、ということである。
この講演はドイツ語(日本語通訳付)で行なわれ、その後、講演内容をめぐるディスカッション(英語/ド
イツ語/日本語)の時間がとってあります。参加は自由ですが、事前にご連絡いただければ、詳しい資料を
お送りします。
連絡先:学習院大学文学部哲学科有川研究室 TEL: 3986-0221 E-Mail: haruo.arikawa@gakushuin.ac.jp
頁頭へ
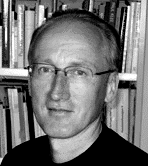 ●9月20日(土) 1時30分
●9月20日(土) 1時30分