 研究テーマ
研究テーマ
Last modified: August 17, 1997
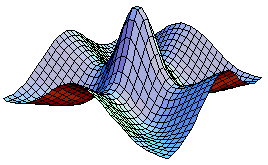 物理学の一つの目標は、我々が(様々な手段で)見る「世界」の中から「普遍的」な構造を抽き出し、それらを真の意味で「理解」することだと思う。
このような営みを着々と積み重ねる事によって、人類全体が少しずつ賢くなっていくのだと信じる。
物理学の一つの目標は、我々が(様々な手段で)見る「世界」の中から「普遍的」な構造を抽き出し、それらを真の意味で「理解」することだと思う。
このような営みを着々と積み重ねる事によって、人類全体が少しずつ賢くなっていくのだと信じる。
私は、非常に多くの(あるいは無限の)自由度を持つ物理系が自由度の間の相互作用によって生み出す「おもしろい」現象を、深く理解することを目指し、主に、統計物理学、固体物理学、場の量子論などの分野で研究を進めてきた。
特に、数学的に厳密で、しかも物理の本質を明らかにするような結果を導くことを目標にしてきた。
具体的な研究テーマはだいたい以下のとおり。
何らかの量子力学系で、量子力学の時間発展則と初期条件についての(ゆるい)仮定のみから平衡統計物理のカノニカル分布を導こうという試み。
以下のように、一般的な描像といくつかの具体例は作ったのだが、真に意味のあるゴールは一体なんなのかさえわからない。
(レター論文(preprint sever にリンク)と、証明の詳細をまとめた informal note(preprint sever にリンク)を公表した。)
-
基本方針:
二つの部分(便宜的に「部分系」、「熱浴」と呼ぶ)からなる孤立した量子系において、「部分系」についての物理量のみを観測することを考える。
適当な条件を満たす純粋状態から出発して、通常の時間発展を行う。
十分に時間がたった後では、例外的な時刻を除けば、「部分系」の全ての物理量の量子力学的期待値が、カノニカル分布による平均と一致することを示したい。
(つまり、ゆらぎを含めて、カノニカル分布が完全に再現される。)
基本的にはたった一回の観測だけを想定していることになるので、観測による系の撹乱の問題などは考えなくてよい。
-
一般的な描像:
全系の定常状態(ハミルトニアンの固有状態)が、"principle of equal weights for eigenstates" と呼ぶ条件を満たし、また、全系の固有エネルギーの分布がある程度「乱れて」いれば、上に書いた意味でカノニカル分布が導かれる。
-
厳密な例:
上の描像が空論ではないことを示すために、厳密な例を作った。
「部分系」はエネルギー準位に縮退がないことを除けば任意。「熱浴」には、状態密度が小さな範囲で一定値をとるという人工的な仮定が課されているが、大まかに見れば、何でもよい。
残念ながら、「部分系」と「熱浴」の相互作用は、「ほぼ弾性的な」とても人工的な形をしている。
しかし、この条件を満たす系については、何の仮定もなく、1 で述べた意味でカノニカル分布が厳密に導かれる。
-
今後の課題(のごく一部):
もっと物理的な例が欲しいところだ。
特に、系の自由度が大きいことや、系が「可積分」でないことがどのように積極的な役割を果たしているかを、はっきりさせてくれるような結果が欲しい。
いわゆる「解ける」モデルは、健全なカノニカル分布、熱力学を生み出すことはないだろう。
だから、「解けない」モデルを使って例を作らなくてはいけないのだが、「解けない」モデルは「解けない」という悩みがある。
exact には解けないけれど、ぎりぎり厳密に解析できるというところを攻める必要があるわけだ。(3 に書いた今回の例も、もちろん exact には解けない。それでも、semiclassical analysys で、部分的に解を厳密にコントロールできた。(この系に対応する古典系はない。semiclassical analysis は理論的な道具としてだけ用いている。))
強磁性体(磁石)の中で電子のスピンが同じ向きにそろう現象を強磁性という。
強磁性の起源を明らかにすることは、物理学における古くからの難問の一つであり、未だに完全な理解への道は遠いと考えられている。
強磁性の問題が難しい一つの理由は、それが電子間の相互作用が十分強いときだけに出現する現象だからである。
従来の固体電子についての理論のほとんどが、相互作用のない電子系からの摂動に基づいていることを思えば、このような「非摂動的な」現象の取り扱いが困難なことも納得できるだろう。
強磁性の起源を議論するための一つの方向として、理想化されたモデルを用いて、強磁性の出現のメカニズムを知ろうという立場がある。
固体中の一つのバンドの電子の運動の自由度と、それらの間の短距離のクーロン相互作用だけを抽出した Hubbard 模型を用いるのが、そういったアプローチでの一つの標準になっている。
しかし、理想化された Hubbard 模型とは言え、強磁性の出現を示すことは容易ではなかった。
1966 年に、長岡は相互作用の強さ U が無限大で、ホールがたった一つという状況では、ある種の Hubbard 模型は完全な強磁性を示すことを証明した。
1990 年代に入るまでは、この長岡強磁性が、Hubbard 模型における完全な強磁性の唯一の厳密な例であった。
(1989 年に Lieb はフェリ磁性の存在を厳密に示した。)
私は、この問題に数年間徹底的に取り組み、以下に述べるようにいくつかの結果を得た。
特に、特異性のない系で(スピン波の存在を含めて)健全な強磁性の存在を証明した仕事は、私としてはこれまでの仕事の中で一番気に入っており、一つの成果であると考えている。
-
長岡強磁性:
長岡の定理の簡潔な証明を与え、その成立条件を拡張した。
-
平坦バンドモデルの強磁性:
1991 年に Mielke が、そして、1992 年に私が、それぞれ、長岡の強磁性とは異なった Hubbard 模型での厳密な強磁性の例を提唱した。
(Mielke のモデルと私のモデルは、共通の性質は持っているが、別のモデルである。)
これらのモデルは、特殊なバンド構造を持っていて、もっともエネルギーの低いバンドのエネルギーが完全に縮退している(分散を持たない)。
これらのモデルについて、クーロン相互作用 U が有限であれば、系は完全な強磁性を示すことが証明された。
これらの強磁性は、今日では「平坦バンド強磁性 (flat band ferromagnetism)」と呼ばれるようになり、長岡の強磁性とは異なった極限的な場合の強磁性として、広く受け入れられるようになった。
-
スピン波励起状態の厳密な評価、および、ほぼ平坦なバンドを持つ系での強磁性の局所的な安定性:
長岡の強磁性が U が無限大という極限的な状況を扱っていたのに対し、「平坦バンド強磁性」は状態密度 D が無限大というまた別の極限的な状況を扱っていた。
当然ながら、 U も D も有限という特異性のない状況での強磁性の例が望まれる。
その方向への第一歩として、私は、平坦だったバンドがわずかに曲がった系において、強磁性状態が局所的に安定な事を示し、さらに、低エネルギーの分散関係が強磁性の系のスピン波として期待される形を持つ事を証明した。
特に、スピン波励起の存在が厳密に示された事は、強磁性の起源の問題への理論的アプローチの中で大切な意味を持っていると思う。
-
特異性のない系での強磁性:
1995 年に発表した仕事では、一般の次元で、次隣接の格子点へのホッピングがあるような一連の Hubbard 模型を取り扱った。
これらのモデルでは、病的な縮退は一切なく、電子のバンドは有限の分散を持つ。
相互作用 U が 0 ならば、これらのモデルは通常の Pauli 常磁性を示し、また U がある程度小さいときには完全強磁性状態は基底状態ではない。
しかし U が(有限だが)十分に大きいときには、基底状態が完全な強磁性を示すことが厳密に示された。
この結果によって、Hubbard 模型は、 U や D が無限大といった極限的な設定でなくても、完全な強磁性を示し得ることがはじめて厳密に示されたといってよいだろう。
また、相互作用の強い多体電子系という立場から見ても、このように純粋に「非摂動的な」現象の存在が厳密に示された例は、ほとんどないと言ってよく、その点にも意味があると思う。
1 次元の反強磁性 Heisenberg 模型は、理想化された固体物理のモデルの中でも、もっとも基本的で、しかも現実性の高いものである。
1983 年に、この古くから研究されていたモデルについての驚くべき予想が発表された。
Haldane によれば、このモデルは、スピンの大きさ S が 1/2,3/2,... といった半奇数であるか、 1,2,... といった整数であるかによって、本質的に異なったふるまいを示すという。
半奇数のスピンの系はエネルギーギャップを持たないのに対し、整数のスピンの系では量子ゆらぎのたまに基底状態は乱れていて、有限のエネルギーギャップを持つというのである。
この予想を出発点にして、整数のスピン、特に S=1 の系における Haldane gap の研究が始まり、大きな流行となり、実験、理論の両側面から様々な成果があげられた。
以下のように、私は Haldane gap の問題の理論的な側面でいくつかの仕事をした。
-
Haldane gap (あるいは、一般に強い量子ゆらぎ)を示す厳密に解けるモデル:
Affleck, Kenndy, Lieb とともに、Haldane gap (とそれに関連する諸性質)の存在を厳密に示すことのできる S=1 の反強磁性スピン系を提唱した。
これによって、Haldane の予言した整数のスピンの系での特異なふるまいが可能であることがはじめて厳密に示された。
このモデルは、 AKLT 模型と呼ばれ、Haldane gap の問題を考察する際の標準的な出発点になっている。
また AKLT 模型の厳密な基底状態である VBS 状態は、Haldane gap 系の量子状態についての直観的な描像を与えるものとして、実験の解釈などの現場でも、頻繁に議論されている。
さらに、高次元でも類似のモデルを構築し、やはり量子ゆらぎのために乱れた基底状態(量子液体)を持つ系があることを示した。
-
隠れた反強磁性秩序、および関連する結果:
Haldane gap 系の基底状態は、量子ゆらぎに乱された無秩序な状態である。
しかし、あるものの見方をすれば、この無秩序な状態の中に「隠れた反強磁性的な秩序」が見いだされる。
これは、den Nijs, Rommelse が発見したことだが、私も独立にこの事実に気づき、Haldane gap 系の相図、磁化過程、擬1次元系でのギャップの問題などの議論に適用した。
-
隠れた対称性の破れ、および、非局所的変換を利用した平均場近似:
Kennedy と私は、 S=1 の反強磁性スピン系における非局所的なユニタリー変換を導入し、Haldane gap 系についての新しいものの見方を提唱した。
これによって、 S=1 の系は「隠れた Z2 x Z2 対称性」を持っていて、Haldane gap 系はこの対称性が完全に破れた相にあるという見方が可能になった。
このような理論的描像によって、エネルギーギャップの存在、隠れた反強磁性秩序の存在、有限系の端状態の存在という Haldane gap 系の3つの特異的な性質が、統一的に理解できる。
さらに、前述のユニタリー変換を用いて、Haldane gap 系における見通しのよい簡単な変分計算(平均場近似)を考案した。
高麗と私は、量子多体系における対称性の破れに関連した一般的な結果を証明した。
これは、数理物理的色彩の濃い仕事だが、Bose condensation や超伝導状態については混乱も多いので、これまでの仕事をもう少し発展させたいと思っている。
-
長距離秩序と対称性の破れの関係:
一般の量子多体系において、対称性を破らない無限系の平衡状態(あるいは基底状態)で長距離秩序があれば、必ず対称性があからさまに破れた平衡状態(あるいは基底状態)があることを証明した。
この定理は、Dyson-Lieb-Simon らによって長距離秩序の存在が証明されている量子反強磁性 Heisenberg 模型に適用するともっとも意味がある。
-
対称性の破れと有限サイズ効果:
秩序パラメターとハミルトニアンが交換しないような量子多体系では、無限系の基底状態で対称性の破れがあっても、有限系の基底状態は(量子ゆらぎのために)対称性を破らない。
そのような状況では、有限系にはエネルギーの低い励起状態がたくさん現れ、それらの線形結合が無限系では対称性の破れた基底状態に収束する。
このような描像は(わかっている人には)以前から信じられていたことだが、我々はこれらの事実を一般的な定理として証明した。
臨界現象との関連もあって、魅力的な分野。
本質的な貢献はしていないが、臨界指数の間に成立する不等式をいくつか証明した。
-
Hyperscaling inequalities:
percolation で成立する不等式。
Hyperscaling 則の等号を不等号に置き換えた形になっているので、上臨界次元以下ではぎりぎり成立していると考えられる。
これによって、percolation の臨界次元が 6 以上であることが示される。
物理的な理解と理論の完成度には素晴らしいものがあり、理論物理・数理物理の観点からは一つの規範となるべき分野である。
実際、統計物理関連の多くの分野は未だに相転移・臨界現象のパラダイムから全く脱却していない(というよりもその縮小版を営んでいる)と思う。
私自身は、(少なからぬ論文や本などを書いてはいるが)この分野への本質的な貢献は(まだ)ない。
多少意味のある仕事をあげると、
-
4 次元での臨界現象:
原と私は、4 次元の(統計力学の)phi^4 模型の理解現象を厳密なくりこみ群を用いて解析した。
磁化率と相関距離の高温側での臨界現象をほぼ完全に解析することができ、古典的な臨界現象に log 的な補正がつくことを証明した。
-
ランダムスピン系の上臨界次元:
percolation での Hyperscaling inequality と同種の不等式を様々なランダムスピン系について証明した。
これから、スピングラスやランダム磁場イジング模型などについての上臨界次元の下限が導かれる。
-
1.99 次元での XY 模型
古典 XY 模型は、2 次元では有限の温度で相転移を起こすが、1 次元では相転移をおこさない。
この途中の次元では、相転移温度は次元 d の関数としてどう変化するのだろうか?
高麗と私は、d<2 であれば、XY 模型は有限温度では相転移を起こさないことを証明した。
つまり、相転移温度は(連続な)次元 d の関数と見たときに、(少なくとも)d=2 で不連続に変化するのである。
面白い結果である。
田崎晴明
学習院大学理学部物理学教室
田崎晴明ホームページ
hal.tasaki@gakushuin.ac.jp