平成7年度重要判例解説
2002.6.20
担当:小島・森本
水不足を理由とする給水拒否の妥当性
―福岡県志免町給水拒否訴訟控訴審判決
<事実の概要>
都市化の進行による人口急増と慢性的水不足に悩む福岡県志免町では、昭和51年以来水道事業給水規則3条の2第1項により分譲住宅・マンション等を建築する場合等は新規給水を拒否、または給水開始の時期を制限することとしていたが、昭和64年に同条項を改正し、新たに給水の申し込みをする者に対して「開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるもの」もしくは「共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合は全戸」に、「給水しない」か「又は給水開始の時期を制限する」と定めた。
東峰住宅産業株式会社(以下X)は、同町内にある土地上に420戸のマンションを建築することを計画し、水道法上の水道事業者である志免町(以下Y)に給水の申し込みをした。これに対してYは規則の定めを根拠にXの給水申し込みを拒否した。そこでXは、Yに対し給水契約の申し込みの承諾等を求める訴えを提起した。
<第一審> 福岡地判平成4・2・13
主位的請求;XがYの水道事業における給水契約上の地位を有することを確認→棄却
予備的請求;YはXの建物の着工又は完成を停止条件として給水せよ→認容
争点 :水道法15条1項は「正当な理由」がなければ需要者からの給水拒否の申し込みを拒絶してはならない旨定めている。給水申し込みを拒否することが同法条項に定める「正当な理由」に基づくものといえるのか。
Xの主張:「正当な理由」とは専ら水道法自体の趣旨・目的からして給水契約の締結の拒否が是認される場合(例えば、経営上技術上給水が困難な場合等)のみを指し、他の行政目的からする拒否はこれに含まない。
Yの主張:この「正当な理由」について、水道法固有の目的によるだけではなく、地方公共団体独自の街づくり計画や水の供給計画による規制も含まれる。
Yは福岡市に隣接して所在するところ、福岡市近郊は都市化が進み人口が急増しているため、Xに対する給水を認めると、他の開発業者も次々とマンション建設に着手して給水申し込みをし、将来的に水が不足する事態を招来することが明らかである。それを見越してXに給水を拒否することは水道法の「正当な理由」に該当する。
判決 :「正当な理由」の解釈については、水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず、その責に帰することのできない理由により給水契約の申し込みを拒否せざるを得ない場合に限られ、水道法の所期する目的以外の行政目的を達することや、単なる将来的な水不足を正当な理由とすることはできない。
<控訴審>福岡高判平成7・7・19
判決 :原判決取り消し・請求棄却
争点1:Yが給水規則3条の2第1項を根拠にXの給水申し込みを拒否することは、水道法15条1項に抵触しないか
Xの主張:第一審の主張に加え、給水規則3条の2第1項は、その性質上、水道法14条第1項にいう供給規程であるところ、これが水道法上の強行規定に反してはならないことはいうまでもない。よって給水規則3条の2第1項が強行規定である水道法15条1項に違反しているならば、この規則を盾に給水規則を拒否することは許されない。
Yの主張:「正当な理由」を判断するに当たっては、水を巡る当該市町村の自然的、社会的諸条件及びその変化に即し、他の行政需要に対する施策等との調和をも視野に入れながら、給水申込者の事情と市町村の事情を総合的に考慮して判断すべきである。
争点2 :給水規則3条の2第1項とは別に、YがXの給水申し込みを拒否し得る水道法上の「正当な理由」があるか。
Xの主張:Yの水事情はXの給水申し込みを拒否しなければならない程ではなく、むしろこれに十分応じることができる状況にある。それにもかかわらずYは「正当な理由」の根拠になりえない給水規則3条の2第1項を盾にXの申し込みを拒否しているものであり、Yに水道法上の「正当な理由」などない。
Yの主張:現在のみならず将来にわたって町民らに安定的に継続して清潔、安価な水を供給するためには、長期的視野に立ち水道行政上の施策を進めなければならず、この場合、需要と供給能力の均衡が失われないよう努めねばならないから、事情によっては需要を抑制することも行政を担当する者のとるべき施策の一つである。
第一審判決と控訴審判決の違い
1、水道法の15条1項の「正当な理由」の解釈
第一審;厳格に解釈
控訴審;やや緩和している。「正当な理由」の有無を判断するに当たり、当該市町村の水を巡る自然的、社会的諸条件やこれに対応する水道行政の実際、給水申込者の事情等、双方の事情を対比、総合的に勘案して、給水の申し込みを拒むのもやむを得ないと認められるときには、「正当な理由」がある。「正当な理由」には具体的事案に応じて様々な事由があり得る。
2、Yの水事情についての認識の差
第一審;Xへの給水を認めても著しく水不足を招来しない。
控訴審;Yの水事情について認可水源だけでは水は足りず、農業用水のヤミ転用などに頼ってきた。よってYの給水努力に怠慢があったとはいえないし、漫然と新規の給水申し込みに応じていると、近い将来住民らの給水需要に応じることができなくなることが容易に予測できる。
※また、新規給水規則が制約される基準を定めた本件給水規則3条の2第1項は、新規給水規則の開始による給水量の増加を抑制するものとして認められ、「20戸(20世帯)」という基準数値はYの水事情及び実際に規制の対象となる者が限られ、その者が規制の対象となるのもやむを得ない面のあることを考慮すると、著しく不合理で妥当性を欠くものとは決め難く、現時点においては一応妥当なものといってよい。よってこの基準数値から外れる新規給水の申し込みに対しては、これを拒みうる「正当な理由」があることを根拠にこれを拒むことができると解するのが相当である。
<最高裁判決> 平成11年1月21日第1小法廷判決
争点:水道法第15条1項にいう『正当の理由』の意義とその有無。
判決:上告棄却
判旨:『正当の理由』の意義…水道事業者の正常な企業努力にもかかわらず給水契約を拒まざるを得ない理由と解される。
※本判決は、原審の事実認定を是認した上、Yは全国有数の人口過密都市であり、今後も人口集積が見込まれ、その水道事業は認可水源のみでは現実に給水量を賄うことができず、いわゆる違法取水により補っているが、法的見地、契約条項の両面から見て右取水は不安定である。このまま漫然と新規の給水申込みに応じていると、近い将来需要に応じきれなくなり深刻な水不足が予測される状態にあるとした。
また、水が限られた資源であることを考慮すれば給水義務は絶対的なものということはで
きず、給水契約の申込みが適性かつ合理的な給水計画によっては、対応することができな
いものである場合、さらに、水道事業者という立場において、専ら水の需要の均衡を保つ
という観点から水の供給量が既にひっ迫している市町村において、急激な水道水の需要の
抑制施策として新たな給水申込みのうち、需要量が特に大きく現住民の生活水を得るため
ではなく住宅供給事業者の住宅分譲目的の契約締結を拒むことには『正当な理由』があり、
やむをえない措置として許されるとした。
→供給義務の例外たる『正当な理由』は、公益事業者としての責務を放棄したことにならないような事由に限られ、その性質上個別的かつ総合的判断が必要であり、数値的基準化が難しい点、同法15条1項の文言自体が極めて抽象的である点から、法全体の主旨や関する規定に照らして合理的解釈が必要である。それに基づいて、Yの具体的な給水事情を踏まえた上で給水申込みに対するYの給水契約の拒否を適法と判断したものであり、本判決から、このような分譲業者の大口の給水申込みに対しては異なる事情の下においても給水拒否が許されると直ちにいうことはできない。
[本判決の特徴]
給水量を増大させる努力を尽くすことが水道事業者の第一主義的な責務であることを強調。水道法の趣旨目的に照らし何が『正当な理由』に該当するかを最高裁が初めて判示した。
最高裁判決と控訴審判決の違い
最高裁判決では、控訴審判決の実質論部分と共通の発想にたって町勝訴の結論を導いたと考えられるが、控訴審判決は、『正当な理由』をやや広めに理解している点や、本件規定を『正当な理由』の具体化として合理的なものであると評価している点が最高裁と違う。
水道法の趣旨目的
① 電機、ガス、放送等と並ぶ公共事業(public utilities)として規律。
公益事業規制が置かれている。
② 給水能力の計画的拡充の指示 (同法1条、2条の2、5条の2)
〔公益事業規制の重要な要素〕
・供給条件(ex.料金)にかかる公的規制 14条
提供されるサービス(本件であれば給水)の価格を中心とする契約内容。
供給規程(水道条例、水道事業給水条例等の名称の条例)に定められており、水道事業経営の厚生大臣認可を受ける際の審議事項である。 (7条8条)
・供給義務(ex.供給契約の締結強制) 15条
公益事業の名のとおり、誰もがサービスの受益者となる地位を保証されること。
→本件給水規則規定のような定めは、内容的に水道法上の供給条件を定めたものとはいえない。
関連訴訟 違法建築物に対する給水留保
(最高裁昭和56年7月16日第一小法廷判決)
<事実の概要>
上告人=原告・控訴人 小西覚一(以下X)
披上告人=被告・被控訴人 豊中市(以下Y)
Xは大阪府豊中市内に賃貸用共同住宅を所有し、増築工事を行いYの建築主事に対し、建築確認の申請をが、この増築部分が建築基準法の建ぺい率に適合しなかったため建築確認は得られないまま、Y水道局に対し、給水装置新設工事の申し込みをしたところ、同水道局職人はその受理を事実上拒絶し、建築基準法違反を是正し、建築確認を受けた後申し込みをするよう勧告をした。このためXは既存給水装置から増築部分へ私設水道装置を設置して水を引き、本件建物を賃貸した。一年半後、改めてYに給水装置工事の申し込みをし、この申し込みは受理され、工事は完成した。Yが違法建築物に給水を行わなかったのは、Yが大阪のベッドタウン化し、違法建築物が増加したための防止策として、違反建築物に対する給水制限実施要綱を定めていたことによる。
XはYの職員が、給水装置工事申し込みの受理を拒絶し、一年半以上の間給水を停止したのは水道法15条第1項に違反し、Xの給水を受けるべき権利を侵害した等としてYに対し、正規の水道装置がないことによる敷地の減価、増築部分の賃料・敷金の減収・慰藉料等の損害賠償として200万円の支払いを求めた。
<一審>:請求棄却
違法な措置ではあるが損害の立証がない。
<二審>:控訴棄却
給水工事の申し込みに対する事実上の拒否は「いまだもって行政指導の限界をこえたもの」とはいえず、「行政法規たる水道法15条に違反するからといって直ちに不法行為上の違法ということはできない」本件建物についての建ぺい率違反は軽微なものとして看過できる事柄ではないこと、Xは違反の是正が可能であるにもかかわらずその意思が全くなかったこと、行政指導の方針である前記実施要綱の趣旨、目的、その他前記事情を総合しんしゃくするとYの措置は行政指導の限界を超えたものということはできない。
<最高裁>:上告棄却
なお、この判決と同様に行政指導が行われているとい理由だけで建築確認処分を留保することは違法だとした判決に最高裁昭和60年7月16日判決(※)、最高裁平成元年11月8日決定がある。(後記武蔵野市長給水拒否事件)
※判旨より;建築主が行政指導に不協力・不服従の意思を表明している場合には当該建築主が受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り、行政指導が行われているとの理由だけで確認処分を留保することは違法である。
水道法一五条の「正当な理由」の解釈 学説
①専ら水道法自体の行政目的から給水契約の締結の拒否が是認される場合をいい、他の行政目的からする拒否は含まれない
②①の場合のほか、給水が申込者の公序良俗違反行為を助けるような場合、あるいは申し込みが権利の濫用になるような場合も含まれるとするもの
③建築基準法の行政目的と水道法の行政目的のように、都市目的のように、都市環境の保全という点で競合する部分がある場合には、競合する部分に違法がある限りにおいてある程度まで給水拒否が許されるが、居住が始まれば違法建築であっても給水拒否は許されないとするもの
④指導要綱が民主的住民参加を経て作成され、内容的にも合理的で正当であれば、ここに従わない者に対する給水拒否は事情により正当の理由があるとするもの
①説について 裁判例 (本判決はこの説を採用)
ⅰ大阪地判昭和42・2・28
土地不法占拠者や違法建築物居住者であるということは正当な理由にならないとした事例
ⅱ長岡簡判昭和42・5・17
ガス供給水道工事につき地主の承諾が得られないことは正当な理由にならないとした
事例
ⅲ大阪高判昭和43・7・31
ⅰの控訴審判決
ⅳ大阪高判昭和53・9・26
関連判例の控訴審判決
①
について 武蔵野市長給水拒否事件
最高裁平成元年11月8日第二小法廷決定
<事実の概要>
昭和46年、武蔵野市長は市議会全員協議会の承認を経て、「武蔵野市宅地開発等に関する指導要綱」を制定した。この要綱は地上高10メートル以上の中高層建築物を建てる際に、要綱に従わない事業主に対し、市は上下水道等必要な協力を行わない旨を規定していた。要綱制定当初から行政指導に反発していたY建設は要綱に従わないまま市に工事用水の給水契約の申し込みをした。これに対し市は、要綱に従わなければ申込書を受理しない旨の応答をした。Yは隣接ビルから強行着工する一方で要綱に定められる要同意住民の過半の同意を得る見通しをつけ、給水申し込みを繰り返したが、市は全関係住民の同意を得ることを求め受理せず、Yは入居者と共に給水契約と下水道使用の申し込みをしたが市は従前の態度を固持した。そこで水道法一五条一項に違反するとして市長が起訴された。
<一審>行政指導の指針に過ぎない指導要綱に法的拘束力はない。行政指導の継続は「正当な理由」当たらない。
<原審>市は指導要綱を順守させるための水道事業者が有している給水権限を用い、指導要綱に従わないYらとの給水契約の締結を拒んだものであり、その給水契約を締結して給水することが公序良俗違反を助長することとなるような事情もなかった。このような場合たとえ指導要綱に従わない者からの申し込みであっても、締結を拒むことは許されない。
上水道の法的性質
従前は、判例・学説ともにこれを公法関係と捉えるものが主流であった。
しかし、昭和38年の地方自治法改正により、水道料金が地方税の滞納処分の例により徴収されるものから外されたこともあって(第231条の3第3項)、判例は私法上の関係であるとするものが支配的になったといえるが、学説の傾向は近年、公法私法の二分を前提にアプローチする方法自体に批判的であり、具体的事実と実定法規に即して判断していくとの立場が強くなりつつある。
学説
・佐々木説・渡辺説・磯崎説
営造物の利用関係はすべて政治活動にかかわるもので公法関係あり、政治生活
か否かは非営利事業か否かで区別されると解する。
・美濃部説
水道は原則としては市町村のみが経営し得べきものであり、その法律関係は公共団体に特有なものとして認められ公法的性質を有するものとされると解する。
・田中説
公企業(営造物)の利用関係を原則的には私法関係と見るが、
① 公企業が一般的に社会公共の福祉の維持増進を目的としていること
② 収支相償うことを建前としていないこと
から、直接実定法が司法と異なる規定を置き、あるいはそのように解釈される場合を公法関係(いわゆる管理関係)と解する。
・山田説
公役務を収益的公務(水道等の供給事業)と福祉的公務に分け、前者は原則として私法関係と解するが、水道の利用規制は法規命令としての性質を有するからそれが特別の定めをしているときにはその限度として公法上の当事者関係となると解する。
・原説
特別規定がない場合でも公共の福祉の実現を目的とする公共施設の特殊性を考慮し、純然たる私法関係とは異なる解釈をせねばならぬことが少なくないと解する。
・原田説
営造物の利用関係を二者択一的に公法関係、私法関係に二分する作業を行いそれに基づいて行政処分の許容性を判断することを批判し、具体的事実と実定法の規定に則して直裁的に見定めて判断すべきものと解している。
判例
・福岡市水道料金条例無効確認請求事件(福岡地判昭30・4・25)
給水債務と料金支払い債務とに関する水道事業である福岡市とその水道使用者との関係は一種の公法関係に立つものと解した例。
・東京地八王子支決昭50・12・8
公営水道使用の法的性格は私法上の当事者関係であると解するとした例。
・岡山地判昭44・5・29
一種の公共用営造物である水道事業の利用関係が公法関係であると解することは相当でないとした例。
・大阪地判昭42・11・30
水道法第15条第1項で水道事業者と使用者が対等の立場に立つ契約関係である旨の文言を使用していることから水道料金債権は私法上の債権であるとした例。
私見
各判決にはおおむね賛成。
本件における慢性的な水不足は、市町村が取水量の増加に努力を尽くしたにもかかわらず、状況が改善しないということから、その地域の自然的条件、社会的条件に影響される一種の不可抗力に近いものであると考えられる。
また、当該地域での大口の新規給水申し込みに応じることは現住民への生活水の供給に支障をきたし、水不足の招来を予見できると解することも妥当である。
《志免町》
福岡県の西部、福岡都市圏のほぼ中心に位置しており、福岡市また福岡空港に隣接した南北に細長い総面積8.7平方キロメートルの県下では6番目に小さな町である。
戦前は海軍炭鉱、戦後は旧国鉄の志免炭鉱と、石炭の町として栄えていたが、昭和39年の閉山でおおきな打撃を受け人口は約1万6000人まで減少した。
しかし、福岡市の中心部まで約8kmという地の利と温暖な気候に恵まれ、昭和40年以降は福岡市のベッドタウンとして住宅開発が進み、人口は着実に増加した。現在、人口は約3万8000人を超え、人口密度は4,160人/平方キロメートルと県内の町村では第1位の町となった。町内には農地は少なく、2つの工業団地があり、機械、金属工業を中心として約170の事業所が立地しており、近年では、町の動脈である近隣の市町村を結ぶ福岡東環状線や県道福岡太宰府線などの幹線道路沿いに大型ショッピング店舗等が進出するなど、新たな商業集積がみられる。
志免町の水源は御笠川や宇佐美川など近郊河川、それに筑後川の3つに分けられる。また、筑後川からの水は福岡地区水道企業団を通じて供給されており、志免町が使うおよそ5分の1をまかなっている。
・平成12年度水源別取水比率 宇佐美川49.5%
御笠川30.1%
企業団(筑後川)20.4%
<参考文献>
・判例時報1438号118頁、1548号67頁、
・ジュリスト増刊 行政法の争点 36頁
・美濃部達吉 公法と私法 59頁
・行政判例百選Ⅰ<第4版>
<参照条文>
志免町水道事業給水処理規則
・3条の2(給水許可の制限等)
新たに給水の申し込みをする者で、次の各号の1に該当する場合は、給水許可を拒否し(開発行為許可済分、開発行為及び建築に係る事前協議分を除く。)、又は給水開始の時期を制限する。
(1)
開発行為又は建築で20戸(20世帯)を超えるものには給水しない。
(2)
共同住宅等で20戸(20世帯)を超えて建築する場合には全戸給水しない。
(3)
一日最大使用量が、10立方メートルを越えて使用するものには給水しない
(4)
前各号に類すると町長が認める場合
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合には、この限りではない。
水道法
(昭和三十二年六月十五日法律第百七十七号)
最終改正:平成一四年二月八日法律第一号
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
(責務)
第二条 国及び地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講じなければならない。
2 国民は、前項の国及び地方公共団体の施策に協力するとともに、自らも、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に努めなければならない。
第二条の二 地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。
2 国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
5 この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
8 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
9 この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
12 この法律において「給水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。
(水質基準)
第四条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 病原生物に汚染され、又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
二 シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。
三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まないこと。
四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。
六 外観は、ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(施設基準)
第五条 水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
一 取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
二 貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
三 導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
四 浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要なちんでん池、濾過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
五 送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
六 配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的で、かつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3 水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4 前三項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、厚生労働省令で定める。
第一章の二 広域的水道整備計画
第五条の二 地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な整備に関する基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。
3 広域的水道整備計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 水道の広域的な整備に関する基本方針
二 広域的水道整備計画の区域に関する事項
三 前号の区域に係る根幹的水道施設の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的事項
4 広域的水道整備計画は、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して定めなければならない。
5 都道府県知事は、広域的水道整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に報告するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
6 厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、広域的水道整備計画に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
第二章 水道事業
第一節 事業の認可等
(事業の認可及び経営主体)
第六条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
2 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとする。
(認可の申請)
第七条 水道事業経営の認可の申請をするには、申請書に、事業計画書、工事設計書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二 水道事務所の所在地
3 水道事業者は、前項に規定する申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 給水区域、給水人口及び給水量
二 水道施設の概要
三 給水開始の予定年月日
四 工事費の予定総額及びその予定財源
五 給水人口及び給水量の算出根拠
六 経常収支の概算
七 料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件
八 その他厚生労働省令で定める事項
5 第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一日最大給水量及び一日平均給水量
二 水源の種別及び取水地点
三 水源の水量の概算及び水質試験の結果
四 水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
五 浄水方法
六 配水管における最大静水圧及び最小動水圧
七 工事の着手及び完了の予定年月日
八 その他厚生労働省令で定める事項
(認可基準)
第八条 水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
一 当該水道事業の開始が一般の需要に適合すること。
二 当該水道事業の計画が確実かつ合理的であること。
三 水道施設の工事の設計が第五条の規定による施設基準に適合すること。
四 給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと。
五 供給条件が第十四条第二項各号に掲げる要件に適合すること。
六 地方公共団体以外の者の申請に係る水道事業にあつては、当該事業を遂行するに足りる経理的基礎があること。
七 その他当該水道事業の開始が公益上必要であること。
2 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
(附款)
第九条 厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。
2 前項の期限又は条件は、公共の利益を増進し、又は当該水道事業の確実な遂行を図るために必要な最少限度のものに限り、かつ、当該水道事業者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(事業の変更)
第十条 水道事業者は、給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするとき(次の各号のいずれかに該当するときを除く。)は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 この場合において、給水区域の拡張により新たに他の市町村の区域が給水区域に含まれることとなるときは、当該他の市町村の同意を得なければ、当該認可を受けることができない。
一 その変更が厚生労働省令で定める軽微なものであるとき。
二 その変更が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるとき。
2 第七条から前条までの規定は、前項の認可について準用する。
3 水道事業者は、第一項各号のいずれかに該当する変更を行うときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止)
第十一条 水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(技術者による布設工事の監督)
第十二条 水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならない。
2 前項の業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
(給水開始前の届出及び検査)
第十三条 水道事業者は、配水施設以外の水道施設又は配水池を新設し、増設し、又は改造した場合において、その新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出で、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならない。
2 水道事業者は、前項の規定による水質検査及び施設検査を行つたときは、これに関する記録を作成し、その検査を行つた日から起算して五年間、これを保存しなければならない。
第二節 業務
(供給規程)
第十四条 水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
2 前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この号において同じ。)が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
3 前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
4 水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
5 水道事業者が地方公共団体である場合にあつては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
7 厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第二項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。
(給水義務)
第十五条 水道事業者は、事業計画に定める給水区域内の需要者から給水契約の申込みを受けたときは、正当の理由がなければ、これを拒んではならない。
2 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
3 水道事業者は、当該水道により給水を受ける者が料金を支払わないとき、正当な理由なしに給水装置の検査を拒んだとき、その他正当な理由があるときは、前項本文の規定にかかわらず、その理由が継続する間、供給規程の定めるところにより、その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置の構造及び材質)
第十六条 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合していないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。
(給水装置工事)
第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。
2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。
3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。
<参考資料> 志免町に隣接する福岡市の気象状況
表1
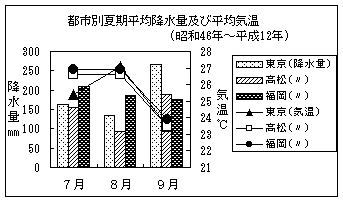
表2
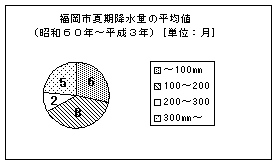
※表2は、7年間の夏期(7月~9月、計21ヶ月間)の降水量に基づき、
それぞれの月数を示したものである。
ちなみに21ヶ月間の平均降水量は約209.1㎜となっている。