●書道史
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
| 神崎 充晴 講師 |
2 |
2〜4 |
第1学期 |
木 |
4 |
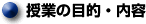
-
漢字の渡来以来、さまざまな変遷を遂げた、わが国の書の歴史を、奈良時代から江戸時代まで、ジャンル別(写経・仮名・古筆・三筆・三跡・墨跡・書流等々)に展望しながら、書の発展過程をさぐる。各時代の文化史的背景を織り込みながら学習する。筆で文字を書かなくなった現在、古い筆跡が読めなくなっている。読めれば、理解がより深まることは必至。毎時間、持参する関連資料(実物を含む)を参照しながら、読む実践を体験しながら、日本の書の歴史を広い視野からとらえてみたい。さらに、他の博物館・美術館の展覧会案内を利用して、実物に接する機会を多く持たせたい。

-
| 1 | 日本書道史と“古筆学” |
| 2 | 日本の書のうつりかわり…日本書道史概観 |
| 3 | 写経の歴史 奈良朝写経と写経所 |
| 4 | 写経の歴史 平安朝貴族の法華信仰と装飾経 |
| 5 | 漢字の渡来と三筆 |
| 6 | 三跡と和様の成立 |
| 7 | 仮名の成立と古今集 |
| 8 | 調度手本と古筆 |
| 9 | 古筆の尊重と古筆切 |
| 10 | 古筆鑑定…古筆家の誕生 |
| 11 | 茶の湯と手鑑…古筆観賞の変遷 |
| 12 | 古筆の筆者推定(1)源兼行と高野切 |
| 13 | 古筆の筆者推定(2)藤原伊房と北山抄 |
| 14 | 古筆の筆者推定(3)藤原定実と元永本古今集 |
| 15 | 古筆の筆者推定(4)藤原教長と今城切 |
| 16 | 古筆学の成果と価値 |

-
すべて講義形式

-
出席・レポート
![]()
![]()
![]()
![]()