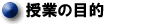
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 中村 滋 講師 | 4 | 通年 | 火 | 5 |
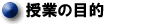
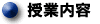
| 1 | オリエンテーション、H1学問としての数学の誕生 |
| 2 | H2ギリシア数学からインド・アラビアの数学へ |
| 3 | H3数学の再生、そして微分積分学の発見 |
| 4 | 関数、極限値、連続関数 |
| 5 | 微分法 |
| 6 | 問題練習1、付・ライプニッツが解いた問題 |
| 7 | 微分法の応用、接線、極値 |
| 8 | テイラー展開、ロピタルの定理 |
| 9 | 問題練習2、付・ニュートンの円周率計算 |
| 10 | 不定積分 |
| 11 | 不定積分のテクニック |
| 12 | 問題練習3、付・オイラーの偉業 |
| 13 | H4解析学の発展 |
| 14 | 定積分 |
| 15 | 定積分の応用 |
| 16 | 問題練習4、付・アルキメデスのやったこと |
| 17 | 多変数関数、偏導関数 |
| 18 | 偏微分の公式たち |
| 19 | 問題練習5、付・曲面 |
| 20 | 2変数関数の極値 |
| 21 | 陰関数定理、様々な曲線たち |
| 22 | 問題練習6、付・定円に内接する面積最大の三角形 |
| 23 | 重積分 |
| 24 | 重積分の応用 |
| 25 | 問題練習7、付・アルキメデス再論 |
| 26 | H5解析学の危機と厳密な解析学の完成 |
| 27 | 総復習と問題練習8 |
|
頭にHとあるところは数学史の話になる。微分積分学の話では3回目毎に問題練習が入り、そこでは学生諸君に問題を解いてもらうと共に、歴史上興味のある問題を取り上げて私が解説を加える。 12月20日は予備日とする。 |



