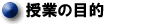
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 福元 健太郎 助教授 | 4 | 3〜4 | 第2学期週2回 | 水 水 |
1 2 |
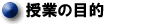
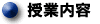
|
扱う政治問題としては、主に3つに焦点を当てる。1つはキリスト教と性の関係である。同性婚、幹細胞研究、古くは中絶の問題は、2004年大統領選挙における大きな争点の1つであったが、これらは今後も燻り続けると思われる。聖職者の幼児虐待も同根である。次に、社会経済的な不平等である。富裕層対貧困層、人種・民族の違いが、福祉、教育、治安、都市などの諸政策に大きな影を投げ落としている。最後に世界秩序構想である。やはり大きな焦点は中東と極東になる。これらの問題について、なるべく2つ(以上)の見方を紹介することで、受講生の思考力を刺激したい。いずれにしても、時事にとらわれず、今後十年は通用するような大きな流れを掴むことを目指す。 実際に扱う論説は、いくつかの雑誌、例えば、The Atlantic Monthly, Business Week, Commentary, Economist, Foreign Policy, The Nation, The New Republic, New Yorker, The New York Times Magazine, The Public Interest, The Weekly Standardなどから選ぶ予定である(Foreign Affairs とNewsweekは邦訳があるので取り上げない)。また下記教科書欄にある書籍などからも適宜抄録する。 |



