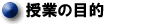
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 大久保 和正 講師 | 2 | 1~4 | 第2学期 | 土 | 2 |
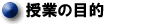
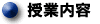
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | 共産主義経済と資本主義経済、古典派経済学とケインズ経済学 |
| 3 | マクロ経済学の基礎(国民所得、金融制度)と貿易収支 |
| 4 | 比較優位の原則 |
| 5 | 為替レート、金利、裁定と投機 |
| 6 | 金融の不安定性、バブルのメカニズム |
| 7 | 金本位制 |
| 8 | 世界大恐慌の進展 |
| 9 | 世界大恐慌の原因とその後の政策(ニューディール政策は成功したか) |
| 10 | 日本の昭和金融恐慌とその後の政策 |
| 11 | ブレトン・ウッズ体制の成立と崩壊 |
| 12 | 固定相場制と変動相場制、自由貿易体制と国家の安全保障 |
| 13 | 政治経済思想(重商主義、自由主義) |
| 14 | 政治経済思想(共産主義、サッチャー・レーガン革命と新保守主義) |
| 15 | オフショア市場の発展と金融自由化の影響(日本・北欧諸国の資産バブル) |
| 16 | ラテンアメリカ諸国の国際金融危機 |
| 17 | 輸入代替政策と輸出促進政策(ラテンアメリカ、インド、東南アジア) |
| 18 | アジア通貨危機 |
| 19 | 香港のカレンシー・ボード制とヘッジファンド |
| 20 | 東欧、ロシアの移行経済 |
| 21 | IMFとワシントン・コンセンサス |
| 22 | 国際通貨体制のあり方と欧州通貨統合 |
| 23 | 中国の経済発展 |
| 24 | 現代日本の政治経済体制(1940年体制、平成不況) |
| 25 | グローバリゼーションの光と影、政治と経済、国家とは何か |
第1学期(国際政治経済 )は上記の12までを予定しています。今後の分析に必要な経済学を説明したあと、先進国における国際金融システムの歴史を紹介する予定です。第2学期(国際政治経済 )は上記の12までを予定しています。今後の分析に必要な経済学を説明したあと、先進国における国際金融システムの歴史を紹介する予定です。第2学期(国際政治経済 )は13以降で、具体的な問題に入っていきます。国際政治経済思想を一通り紹介したあと、金融のグローバル化に関連して発展途上国に発生した諸問題を扱いながら、「グローバリゼーション」の問題の本質を明らかにしていきたいと思います。 )は13以降で、具体的な問題に入っていきます。国際政治経済思想を一通り紹介したあと、金融のグローバル化に関連して発展途上国に発生した諸問題を扱いながら、「グローバリゼーション」の問題の本質を明らかにしていきたいと思います。国際政治経済  と と は相互に関連していますので、極力通年で履修するようにしてください。 は相互に関連していますので、極力通年で履修するようにしてください。
|


 学年末テスト50%、
学年末テスト50%、 課題図書についての書評30%、
課題図書についての書評30%、 出席・授業への貢献20%、とします。具体的な課題図書は講義の際に紹介します。学期中に新書版2冊程度の分量を読むことをめどとします。
出席・授業への貢献20%、とします。具体的な課題図書は講義の際に紹介します。学期中に新書版2冊程度の分量を読むことをめどとします。



 は準備、
は準備、 は本論と相互に関連していますので極力通年で履修してください。どうしても
は本論と相互に関連していますので極力通年で履修してください。どうしても だけを履修したい学生は、
だけを履修したい学生は、 で配布したレジュメ(当方で用意します)と上記にあげた竹森俊平『世界経済の謎―経済学のおもしろさを学ぶ』東洋経済新報社1999を事前に読んできてください。
で配布したレジュメ(当方で用意します)と上記にあげた竹森俊平『世界経済の謎―経済学のおもしろさを学ぶ』東洋経済新報社1999を事前に読んできてください。