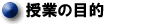
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 藤原 義久 講師 | 4 | 2〜4 | 通年 | 水 | 2 |
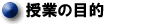
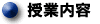
| 1 | はじめに。今年度の講義内容、進め方などについてのガイダンス。 |
| 2 | ヨーロッパ音楽について。歴史の概観。 |
| 3 | 〃 |
| 4 | 〃 |
| 5 | ドビュッシーと近代フランス音楽について |
| 6 | 〃 |
| 7 | 〃 |
| 8 | 〃 |
| 9 | 〃 |
| 10 | 〃 |
| 11 | 〃 |
| 12 | 〃 |
| 13 | ストラヴィンスキーとその影響 |
| 14 | 〃 |
| 15 | 〃 |
| 16 | シェーンベルクとその影響 |
| 17 | 〃 |
| 18 | 〃 |
| 19 | 〃 |
| 20 | 〃 |
| 21 | バルトークとその影響 |
| 22 | 〃 |
| 23 | 〃 |
| 24 | 〃 |
| 25 | 〃 |
| 26 | 近代音楽と現代音楽文化について |
| 27 | 〃 |
| 28 | まとめ |
| 音楽に関する講義なので、初歩的な楽典の知識があると、より理解が深まると思う。 |




