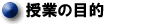
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 福井 憲彦 教授 | 4 | 2〜4 | 通年 | 木 | 4 |
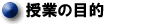
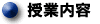
|
1 本年度のゼミに関する全体的な説明を私からした後、参加者の自己紹介 2 図書館において、インターネットを使用した文献検索の実際に関するガイダンス 3 参考図書や目録類、辞典類に関するガイダンス、ティーチング・アシスタントから学部時代の勉強の進め方に関するガイダンス、時間があれば、3年生以上の履修学生による個別報告を開始 4 3年生以上の履修学生による個別報告 5 3年生以上の履修学生による個別報告 6 2年生の履修学生による個別報告 7 2年生の履修学生による個別報告 8 ポーターのテクストの輪読(個別報告の回数は履修学生の数によって変動します。史学科1年生の研修旅行に私が参加できる場合には1回休講が入ります) 9 ポーターのテクストの輪読 10 ポーターのテクストの輪読 11 同上、および第1学期の総括 12 夏合宿の総括 13〜 第2学期は、基本的にポーターのテクスト輪読を通じて専門論文を読む訓練をする ポーターのテクストに関する総括討論を、できれば行う予定 12月の2または3回は履修学生全員との個別面談にあてる予定。時間が足りなければ、昨年度同様、補講期間に一日使用して補う予定。 1月の最終回は、「卒業論文の書き方」について講義する 履修学生数に応じて、進行状況には変動がある。履修学生は全員、各自の研究関心や勉強の進行状況について、年間最低3回の報告を義務づけられる。すなわち、年度初めの報告、夏合宿での報告、学年末リポートの合計3回。これらをクリアしないものは成績評価の対象としない。夏の合宿は、海外研修などの特別の場合を除いて、参加を原則とする。時間的な余裕との関係があり、毎年実現が難しいのではあるが、ヴィデオを皆で見て討論をするような回を、できれば設定したいと考えている。ゼミ幹事を中心に、履修している学生の勉強に関する希望はできるだけ尊重する。 |



