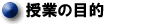
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 高田 博行 教授 | 4 | 3 | 通年 | 火 | 3 |
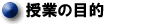
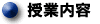
| 次のテーマ群のなかから、受講生たちの希望に応じていくつかを取り上げる:1)カール大帝によるドイツ語奨励(8世紀)、2)修道僧たちの書き残したドイツ語(10・11世紀)、3)宮廷人が愛を歌ったドイツ語(12・13世紀)、4)官房事務官・商人の綴ったドイツ語(14・15世紀)、5)ルターが苦心した聖書ドイツ語翻訳(16世紀)、6)三十年戦争時の文化的砦としてのドイツ語(17世紀)、7)哲学者・数学者ライプニッツのドイツ語コンプレックス(1700年前後)、8)身分語としてのドイツ学生語(17〜19世紀)、9)市民階級の言語的マナーとタブー(18・19世紀)、10)グリム兄弟の辞書づくり(19世紀)、11)ドゥーデンによる正書法辞典の誕生(19世紀)、12)ナチズムにおける言語操作、13)東ドイツのドイツ語、14)掲示板(BBS)のドイツ語。 |


