|
使用するテクストはアラン・フィンケルクロートが2002年に出したものです。ここには当然マンハッタンの出来事は出てきますが、それだけではなく、旧ユーゴ情勢の反省からユダヤ人の被迫害の歴史やパレスチナの錯綜にいたるまでの政治や戦争のこと、バイオ=テクノロジー問題から、それこそケータイ是非にいたる論議まで、ある哲学者が目前で起こり、起こったさまざまな現象について、無理にテーゼふうにまとめてしまうのでも、急いで価値判断をするのでもなく、事柄を素直に受けとめ、それについて思考をめぐらせるというかたちで痕跡を書きとめた日録です。わたしは必ずしもこの語り手の意見に賛成できないところもありますが、それはそれ、このエッセイのアンテナはなかなかなものだと思いますし、中身も興味深いと思います。日録ふうの記述ですから、きわめて雑多にいろんなことが語られていますが、それぞれは短いもので(一日当たり大体長くて三頁前後)、非常にラコニックに、かつまた、皮肉をたっぷり効かせた記述だといえます(それだけに丹念に読まないと読みとれないところもかなりあります)。これを、昨年度読んだ日付けの続きから読む予定です。一冊すべてを一年で読みきることはたぶん無理ですが、なるべく多角的に読むことができるに如くはないと考えています。ときに難しい箇所もあろうと思いますが、仏文の卒業年次生でこの程度のものにまったく歯が立たないのではちょっとどうかなと、それはないだろうと、まあ期待しているわけです。知識不足でわかりにくい箇所は予備的に調べてもらい、かつまた、わたしが自分の知ることを媒介に極力リードしながら、演習形式で進みます。フランスの内政に関わって、われわれにはあまり馴染みのない事柄は飛ばして、本質的で大事だと思える章をゆっくり読むつもりです。題材はなんであれ、考えることがもっとも大切だし、それが要求されるでしょう。また、考えることは、やってみれば面白いのだ、喰わず嫌いだったのだということが心底体感できるといいなと幻想しています。
|
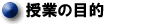
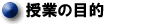
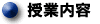


 sent, nrf. Gallimard, 2002
sent, nrf. Gallimard, 2002
