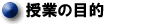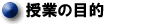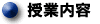| 1 |
法理学とはどんな学問か(その歴史、他の学問との関係、主要文献案内) |
| 2 |
法理学とはどんな学問か(前回の続き) |
| 3 |
法と道徳(この二つの言葉の多義性。両者の相違と相互関係。「法の外面性」と「道徳の内面性」)[「権利と人格」第1章] |
| 4 |
法と道徳(前回の続き) |
| 5 |
権利を基礎に置く道徳(功利主義などの帰結主義と義務論との比較。人権理論のさまざま)[「権利と人格」第2章] |
| 6 |
権利とは何か、また何のためにあるのか?(「選択説」対「利益説」)[「権利と人格」第3章] |
| 7 |
権利の道徳だけで十分か?(「共通善」の政治。未来の世代)[「権利と人格」第4章] |
| 8 |
人格の概念再考(人格の同一性と別個性。共同体主義対個人主義。社会的人格観)[「権利と人格」第5章] |
| 9 |
人格の概念再考(前回の続き) |
| 10 |
自己所有権と財産権(財産権と「人格的」権利。労働所有権。有体財産と無体財産)[「自由はどこまで可能か」第2章] |
| 11 |
自己所有権と財産権(前回の続き) |
| 12 |
権利の救済方法(刑罰否定論。私的な権利執行)[「自由はどこまで可能か」第3章] |
| 13 |
「社会」とは何か? 「国家」「政府」とは何か?[「自由はどこまで可能か」第4章] |
| 14 |
家族関係を法律で規制する必要はあるのか?[「自由はどこまで可能か」第5章] |
| 15 |
リバタリアニズムへの批判や疑問[「自由はどこまで可能か」残りの部分] |