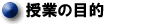
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 神前 禎 教授 | 2 | 3 | 第2学期 | 水 | 2 |
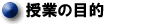
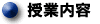
| 1 | ・本授業の趣旨・目的、および、授業進行上の方針・方法について説明 |
| 2 | ・契約準拠法――当事者自治、客観的連結 契約の準拠法について、当事者による準拠法の合意が存在する場合(法例7条1項)と、存在しない場合(同2項)とに分けたうえで、当事者自治の原則の意義と根拠、行為地への連結の妥当性、隔地的契約の場合の処理(9条)などについて検討する。また、いわゆる特徴的給付の理論を初めとする、行為地以外の客観的連結の基準についても紹介する。 |
| 3 | ・特殊な契約類型(消費者契約、労働契約)、法律行為の方式 消費者や労働者などの弱者保護の要請がある契約類型における準拠法選択のあり方を検討し、当事者自治の原則の限界について考察する。その後、法律行為の方式について法例8条及び22条を取り上げて検討する。 |
| 4 | ・事務管理・不当利得・不法行為、不法行為における損害額の算定 法例11条を取り上げていわゆる法定債権の準拠法について検討する。不当利得の準拠法と契約等他の法律関係の準拠法との関係、不法行為の原因事実発生地の確定などが検討の中心となる。併せて、最判平成9年1月28日等を取り上げて、わが国における不法行為による損害賠償額の算定の問題についても触れることとする。 |
| 5 | ・物権と担保物権 法例10条の規定する物権の準拠法に関して、所在地法主義の意義、所在地の変更、船舶担保権に関する所在地法と登録地法との関係等を検討する。自動車の譲渡に関する最近の最判平成14年10月29日などが重要な素材となる。 |
| 6 | ・知的財産権 国際的な局面における知的財産権の保護について、並行輸入に関する最判平成9年7月1日、特許に基づく差止請求に関する最判平成14年9月26日などを取り上げて検討する。 |
| 7 | ・債権譲渡と相殺、債権の対外的効力、債務引受 債権譲渡を中心とする、3人以上の当事者が関係する債権債務関係について、関連する各種法制度の連続性を考慮しながら検討する。債権譲渡については法例12条を中心に、債権質についての最判昭和53年4月20日も取り上げて検討する。債権者代位等のいわゆる債権の対外的効力及び債務引受については、現行法上どこに位置づけて解釈するかが中心的な課題となる。 |
| 8 | ・法人、代理、信託 法人に関しては、法人の従属法としての設立準拠法主義の根拠とその適用範囲が検討の中心となる。法人の設立との関係で信託を、また法人代表との関係で代理を併せて扱うこととする。さらに、法人については外国法人の認許(民法36条)や外国会社(商法479条以下)といった実質法上の問題にも立ち入って関連する制度の全体像を明らかにするよう努める。 |
| 9 | ・国際裁判管轄1――総論・裁判権免除 国際裁判管轄と国内土地管轄の違いや国際裁判管轄と民訴法の規定の関係といった基本的な知識を確認した後、最判平成14年4月12日等を取り上げて、裁判権免除の問題を検討する。 |
| 10 | ・国際裁判管轄2――判例理論 最判昭和56年10月16日、最判平成9年11月11日を中心に、財産関係事件におけるわが国の国際裁判管轄に関する判例法理を検討する。検討の対象の中には、合意管轄についての最判昭和50年11月28日、不法行為の裁判籍の一応の証明や併合請求の裁判籍に関する最判平成13年6月8日などが含まれる。 |
| 11 | ・外国判決の承認1――承認要件 外国判決の承認に関する民訴法118条を取り上げ、そこで規定されている承認要件について、懲罰的損害賠償を認めた外国判決の承認可能性、判決主文に現れない利息分についての承認可能性、わが国で審理判断する場合との国際裁判管轄の判断基準の異同、外国からの直接郵送により裁判手続が開始された場合の問題、手続的公序と実体的公序の順に取り上げる。 |
| 12 | ・外国判決の承認2――承認の効果、執行 前回に引き続いて、民訴法118条の承認要件として相互の保証を取り上げ、その後民事執行法24条を中心に、自動承認の原則や外国判決に基づく執行手続について概観する。 |
| 13 | ・国際的訴訟競合、国際仲裁 国際裁判管轄及び外国判決の承認の問題の総括として、いずれとも関連する国際的訴訟競合の処理について検討した後、裁判外の紛争解決手続として国際取引において広く用いられている仲裁を取り上げて検討する。 |
| 14 | ・国際倒産 国際倒産の問題について、破産法といった各倒産法及び、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律を取り上げて制度を概観する。その後、倒産国際私法といった規定の置かれていない問題にも触れることとする。 |
| 15 | ・本授業のまとめ |
| 国際私法分野における基本法である法例は、近く改正が予定されている。本講義では、立法過程の進行に合わせて、中間試案等にも適宜触れることとする。 |



