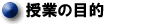
| 担 当 者 | 単 位 | 配当年次 | 開講期間 | 曜 日 | 時 限 |
| 齋藤 登 講師 | 2 | 2〜4 | 第1学期 | 月 | 3 |
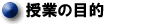
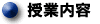
| 1 | 文字の書体、名称を明確にする。(甲骨〜楷書)まで全八体の説明。 |
| 2 | 一番最後に表われた楷書の説明と成立ち。 |
| 3 | テキストで必ず取り上げられる唐代楷書の説明と書き方について。 |
| 4 | テキストで一歩踏み込み日本古代楷書の関係を探る。 |
| 5 | 王羲之を中心とした行書の名品と書き方の説明。 |
| 6 | 平安時代の行書と、晋〜清の行書の関連と相違を見る。 |
| 7 | 草書の代表「書譜」と、「十七帖」の重要性を探る。 |
| 8 | 王羲之より孫過庭までの草書と、それ以後の連綿草の説明。 |
| 9 | 隷書の名品と言われる後漢の諸碑解説と書き方。 |
| 10 | 隷書の成立時より八分隷の完成を解説。 |
| 11 | 秦小篆と戦国篆の相違点と共通点を探る。 |
| 12 | 殷・甲骨文字の神秘性と感性の説明。 |
| 13 | 周・金文に見る古代国家と文字の関連を説明。 |


