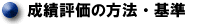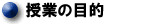
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 水田 健 講師 | 4 | 2~4 | 通年 | 月 | 1 |
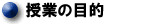
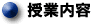
| 1 | 【0】経済学の歴史概観:重商主義から現代までの経済学を概観 |
| 2 | <経済学の古典的世界> 【1】重商主義と開発主義あるいは貨幣【1-1】重商主義の思想と理論:トマス・マンからステュアートまで |
| 3 | 【1-2】重商主義と開発主義あるいは後発国:重商主義と開発主義、市場の失敗か政府の失敗か |
| 4 | 【1-3】重商主義とその後の貨幣経済学:重商主義と貨幣数量説・ケインズの貨幣経済学、貨幣数量説と銀行学派 |
| 5 | 【2】自由競争と自由貿易の経済学 【2-1】スミス道徳哲学と「見えざる手」の理論:自由放任思想は無政府資本主義か? |
| 6 | 【2-2】スミス「自然的自由の制度」と重商主義批判-自由競争の経済学-:分業と資本蓄積による経済成長、自然的投資順序による産業構造の変化 |
| 7 | 【2-3】経済的自由主義と所有・市場・政府:古典派経済学、新古典派経済学、ケインズ、マルクス、べヴァリッジ、ハイエク |
| 8 | 【2-4】リカードウの資本蓄積と経済成長-発展的社会像-:資本蓄積と人口増加、農業の収穫逓減、賃金と利潤の相反関係 |
| 9 | 【2-5】比較生産費説とリストの保護主義-自由貿易の経済学-:比較生産費説と自由貿易、リスト発展段階論と保護主義 |
| 10 | 【3】搾取と資本主義批判-マルクスは死んだか- 【3-1】マルクスの資本主義観:マルクス商品・貨幣論、ポランニーの擬制商品論 |
| 11 | 【3-2】マルクスの資本主義批判と反批判:剰余価値論による資本主義批判、ベームによる搾取利子説批判、資本主義と階級格差 |
| 12 | 【4】歴史と制度の経済学―経済学における歴史と制度再考―:ドイツ歴史学派、制度学派、新制度学派と取引費用理論、制度は外生的か? |
| 13 | <経済学の現代的世界> 【5】効用と稀少性の経済学-新しい経済学の誕生-【5-1】限界革命とはなにか:限界効用理論と限界分析、一般均衡理論 |
| 14 | 【5-2】価値・価格分析の歴史と限界効用理論:価値・価格分析の歴史、水とダイヤモンドの逆説と限界分析による効用理論の洗練化 |
| 15 | 【5-3】ジェヴォンズ限界効用理論と交換の理論:ジェヴォンズの限界効用理論、交換の理論と効用の極大化 |
| 16 | 【5-4】メンガーにおける経済と経済財-欲望と支配可能量-:メンガーによる経済の定義と経済財、メンガー交換の理論 |
| 17 | 【5-5】ワルラス一般均衡理論―経済学における相互依存性の発見―:社会的富の分類、生産の理論における一般均衡理論の展開 |
| 18 | 【5-6】限界効用分析から無差別曲線分析へ―ミクロ経済学の洗練化―:基数的効用から序数的効用へ、無差別曲線分析の発展 |
| 19 | 【6】ケインズと古典派体系【6-1】大不況下のケインズとシュムペーター 有効需要理論か景気循環論か |
| 20 | 【6-2】古典派体系と完全雇用理論:労働市場での完全雇用、セー法則、貨幣数量説と古典派的二分法 |
| 21 | 【6-3】貨幣経済論とケインズ有効需要理論―マクロ経済学の誕生―:ヴィクセル貨幣経済論とケインズ、有効需要理論と不完全雇用均衡 |
| 22 | 【6-4】ケインズ経済学の受容とその批判:ケインズ経済学の受容と新古典派総合、マネタリズムと合理的期待形成仮説 |
| 23 | 【7】古典派経済学の復興とポスト・ケインジアンそしてマルクス:スラッファ、ポスト・ケインジアン、レギュラシオン理論、アナリティカル・マルクシズ |
| 24 | 【8】経済学の現代的世界とその可能性:あらためて20世紀の経済学を概観 |
| 基本的には上記計画どおり行なうが、若干の短縮あるいは延長はありうる。 |