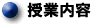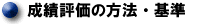| 1 |
ガイダンス(授業の概要と考え方) |
| 2 |
ことわざとは何か−定義という呪縛から脱し、ことわざ研究の必要性を考える− |
| 3 |
学問・知の母胎としてのことわざ−俗信とことわざ− |
| 4 |
ことわざは規範か−法・道徳とことわざ− |
| 5 |
時を超えることわざ−シュメールのことわざ、世俗諺文、北条氏直時分諺留− |
| 6 |
いろはかるたのことわざ(1)−発生と展開− |
| 7 |
いろはかるたのことわざ(2)−庶民の生き方と教育− |
| 8 |
芸能とことわざ |
| 9 |
日本文学とことわざ |
| 10 |
外国文学とことわざ |
| 11 |
方言とことわざ(1)−ウチナーグチを中心に− |
| 12 |
ことわざ研究の方法(1)−文献とフィールドワーク− |
| 13 |
ことわざ研究の方法(2)−比較・対照・構造− |
| 14 |
海を越えてきたことわざ(1)−二兎を追う者は一兎も得ず、一石二鳥− |
| 15 |
海を越えてきたことわざ(2)−艱難汝を玉にす、時は金なり、天は自ら助くる者を助く− |
| 16 |
海を越えてきたことわざ(3)−溺れる者は藁をもつかむ、一桃腐りて百桃を損ず− |
| 17 |
海を越えてきたことわざ(4)−鉄は熱いうちに打て、木を見て森を見ず− |
| 18 |
韓国・中国のことわざと日本のことわざ |
| 19 |
方言とことわざ(2)−共通性と地域性− |
| 20 |
ことわざのなかの数−数の民俗学− |
| 21 |
ことわざの図像学 |
| 22 |
ことわざの批評性−見立ていろはたとえ− |
| 23 |
ことわざとユーモア |
| 24 |
創作ことわざの展開 |
| 25 |
ことわざ研究の現状と未来(1) |
| 26 |
ことわざ研究の現状と未来(2) |