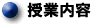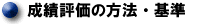●
※表象文化制度論演習
―社会の表象体系としての演劇―
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
| 松井 憲太郎 講師 |
4 |
2〜4 |
通年 |
火 |
5 |

-
日本そして海外において、現代演劇を中心とした舞台芸術は、社会における人間のあり方、文化や思想の状況、そして社会の構造や制度などに対して鋭い批評的な関係意識を持った芸術家たちによって生み出されている。また、こうした舞台芸術の作品は「劇場」や「フェスティバル」など、とくにヨーロッパでは公的な制度として確立された場やシステムを通じて制作され上演されている。
この演習の前半では、現在の日本をふくめた世界の舞台芸術が、劇場やフェスティバルといった、公的に打ち立てられた制度であると同時に、舞台芸術家自身も運営主体として参画する場やシステムを媒介にしながら、どのような形で社会の文化的な領域に結びつき、相互的な影響関係を築こうとしているのか、またそれらの活動を通じて舞台芸術が社会的に果たしている機能とはどのようなものであるかを、具体的な事例検討も行いながら学んでいく。
演習の後半では、範囲を日本の近現代演劇に絞り、岸田國士、別役実、平田オリザ、永井愛などの劇作家の戯曲を講読する。それらの戯曲のあり方を分析、解釈することを通じて、明治末に近代劇として生まれた新劇からアングラをへて現代の小劇場演劇にいたる日本の演劇が、どのように社会を表象しようとし、また社会の文化的な変革を促す芸術の体系として機能しようとしてきたかを考察する。
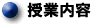
-
| 1 |
日本の演劇および劇場史概論 |
| 2 |
社会と演劇の関係形成についての試論 |
| 3 |
劇場運営論1
運営ポリシーと芸術方針 |
| 4 |
劇場運営論2
海外の公共劇場 ドイツ |
| 5 |
劇場運営論3
演劇フェスティバル フランス |
| 6 |
劇場運営論4
ドラマトゥルグ1 |
| 7 |
劇場運営論5
ドラマトゥルグ2 |
| 8 |
演劇と教育 |
| 9 |
演劇創造の実践例1 日本 |
| 10 |
演劇創造の実践例2 日本 |
| 11 |
演劇創造の実践例3 ヨーロッパ |
| 12 |
演劇創造の実践例4 アジア |
| 13 |
演劇と国民国家 |
| 14 |
演劇と言語 |
| 15 |
戯曲講読1 |
| 16 |
戯曲講読2 |
| 17 |
戯曲講読3 |
| 18 |
戯曲講読4 |
| 19 |
戯曲講読5 |
| 20 |
戯曲講読6 |
| 21 |
戯曲講読7 |
| 22 |
戯曲講読8 |
| 23 |
戯曲講読9 |
| 24 |
戯曲講読10 |
| 25 |
戯曲講読11 |
| 26 |
戯曲講読12 |

-
第1学期の演習では、授業ごとに講師の側が用意した資料(映像資料を含む)をもとに講義形式で進めます。
第2学期では、第1学期末に戯曲を講読文献として指定しますので、それを各授業前までに読み、それらを素材にして演習を進めます。
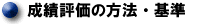
- 学期末レポート提出
- 第2学期末にレポートを提出し、それに基づいて採点します。レポートの課題は授業時に指示します。