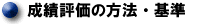| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 相澤 真一 講師 | 2 | 1〜4 | 第2学期 | 金 | 2 |

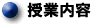
| 1 | (9/18) イントロダクション |
| 2 | (9/25) 統計的検定の考え方(復習)(第1回ミニレポート出題) |
| 3 | (10/2) 統計的推定の考え方(1) |
| 4 | (10/9) 統計的推定の考え方(2) |
| 5 | (10/23)平均値に関する推定と検定(第1回ミニレポートを提出) |
| 6 | (11/6) 回帰分析の基礎 |
| 7 | (11/13)回帰分析の応用(1)(第2回ミニレポートを出題) |
| 8 | (11/20)回帰分析の応用(2) |
| 9 | (11/27)ロジスティック回帰分析 |
| 10 | (12/4) 回帰分析の応用例を読む(1) |
| 11 | (12/11)回帰分析の応用例を読む(2)(第2回ミニレポートを提出) |
| 12 | (12/18)データ分析の中間報告の検討と報告書の書き方 |
| 13 | (1/8) まとめ・社会統計学の応用法(最終レポートの締切はこの日かあるいは1月下旬とする予定) |
|
第2学期はオンライン集計で補いきれない部分を統計分析ソフトを用いて分析してもらいます。受講人数や受講者の皆さんのパソコン環境に対応できるようにしますが、受講者数が多い場合は、パソコン課題はすべて授業時間外に行ってもらう可能性もあります。 第1学期同様、数学やパソコンの知識は前提としませんが、やる気と根気は必要です。また、どうしても必要な数学的トピックは授業内で補います。 |