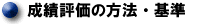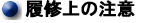| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 荒川 正明 教授 | 4 | 2〜4 | 通年 | 木 | 1 |

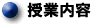
| 1 | オリエンテーション |
| 2 | やきものの種類(1) |
| 3 | やきものの種類(2) |
| 4 | 素材のこと −土と粘土 |
| 5 | 成形のこと −手づくねからロクロまで− |
| 6 | 焼成のこと −炎と窯− |
| 7 | 釉薬のこと |
| 8 | 絵付けのこと |
| 9 | やきものの産地(1) |
| 10 | やきものの産地(2) |
| 11 | やきものの産地(3) |
| 12 | 土器(縄文・弥生・土師器等) |
| 13 | 陶器(1)(須恵器) |
| 14 | 陶器(2)(中世陶器) |
| 15 | 陶器(3)(中世陶器) |
| 16 | 陶器(4)(桃山陶器 ) ) |
| 17 | 陶器(5)(桃山陶器 ) ) |
| 18 | 陶器(6)(京焼) |
| 19 | 磁器(1)(肥前磁器・初期伊万里) |
| 20 | 磁器(2)(古九谷様式) |
| 21 | 磁器(3)(柿右衛門様式) |
| 22 | 磁器(4)(鍋島様式) |
| 23 | 磁器(5)染付と色絵 |
| 24 | 近現代のやきもの(1) |
| 25 | 近現代のやきもの(2) |
| 26 | やきものの名作(1) |
| 27 | やきものの名作(2) |
| 28 | やきものの名作(3) |
| 展覧会など実際に作品に近づく機会をなるべくもちたい。 |