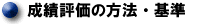| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 高橋 朋子 講師 | 4 | 2〜4 | 通年 | 木 | 3 |

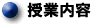
| 1 | 導入 −13、14世紀イタリア美術− |
| 2 | 15世紀前半のイタリア美術 −都市の美術状況− |
| 3 | 15世紀前半のイタリア美術 −宮廷の場合− |
| 4 | 職人としての訓練と学習 −素描を通じて− |
| 5 | 職人としての訓練と学習 −版画を通じて− |
| 6 | 芸術家とパトロン −15世紀の状況− |
| 7 | 芸術家とパトロン −16世紀の場合− |
| 8 | 古代に対する関心(1) −15世紀前半− |
| 9 | 古代に対する関心(2) −15世紀後半− |
| 10 | 諸芸術比較論争(パラゴーネ) −レオナルド・ダ・ヴィンチ− |
| 11 | イメージと古代のテクスト(1) |
| 12 | イメージと古代のテクスト(2) −エクフラシス− |
| 13 | 16世紀のエクフラシス −ティツィアーノの場合− |
| 14 | 試験 |
| 15 | 絵画と彫刻のパラゴーネ −15世紀の場合− |
| 16 | 絵画と彫刻のパラゴーネ −16世紀の場合− |
| 17 | 絵画と彫刻のパラゴーネ −ティツィアーノとミケランジェロ− |
| 18 | 人文主義者と画家 −カスティリオーネとラファエロ− |
| 19 | 画家の自画像(1) |
| 20 | 画家の自画像(2) |
| 21 | 君主の肖像画 |
| 22 | 妻の肖像画 |
| 23 | 恋人の肖像画 |
| 24 | 人文主義者の肖像画 |
| 25 | 皇帝の肖像画 |
| 26 | 教皇の肖像画(1) |
| 27 | 教皇の肖像画(2) |
| 28 | 試験 |
| 授業計画は先に記した内容を予定しているが、実際講義を始めた時点で順番が入れ替わることもある。また内容によっては1度で終わらない場合も予想される。その結果計画がすべて消化できないことも重々考えられることを断わっておく。 |