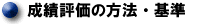●
比較芸術学演習I
―日本の芸術論―
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
| 新川 哲雄 教授 |
4 |
2〜4 |
通年 |
木 |
4 |

-
日本文化における芸術の諸相を取上げて、その特質について考えることを目的としています。そのために、日本における芸術の諸領域(芸能をも含めます)をめぐる言説を対象とし、丁寧な解読につとめることによって問題の理解を深めていきたいと思います。その結果、これは日本文化においてのみ見られることではなく、他地域の文化においても多く見られることなのですが、芸術と宗教との関わりを考えていくことになろうと思います。その際、古代から近現代にわたる様々な文献(できるだけ1回で講読できるくらいの長さのものを、受講者の問題関心にそった内容や領域を考えて、取上げていこうと思っています)の講読・検討と同時に、それをめぐる研究論文の講読をもあわせて行なうことも考えています。また、当然のことながら、諸芸術をめぐる言説は、それら芸術領域で生み出された作品と深く関わっていますので、関連する作品をも視野に入れた問題の検討を考えています。そこで、佐野先生の美術史演習
 と有機的な連携をもって、年間の授業内容を構成していきます。この演習と併せて、美術史演習
と有機的な連携をもって、年間の授業内容を構成していきます。この演習と併せて、美術史演習 の受講を期待します。
の受講を期待します。
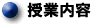
-
| 1 |
授業内容・方法の紹介と問題関心の確認 |
| 2 |
日本の芸術をめぐる言説 |
| 3 |
ゲスト発表(院生によるものを考えています) |
| 4 |
文献講読 |
| 5 |
〃 |
| 6 |
〃 |
| 7 |
〃 |
| 8 |
〃 |
| 9 |
〃 |
| 10 |
〃 |
| 11 |
〃 |
| 12 |
〃 |
| 13 |
日本の芸術をめぐる言説 |
| 14 |
文献講読 |
| 15 |
〃 |
| 16 |
〃 |
| 17 |
〃 |
| 18 |
〃 |
| 19 |
〃 |
| 20 |
〃 |
| 21 |
〃 |
| 22 |
〃 |
| 23 |
〃 |
| 24 |
〃 |
| 25 |
日本の芸術をめぐる言説 まとめ まとめ |

-
第1、2学期とも、私の方からの講義によって問題の所在を確認し、研究対象となる言説の論点の解説を行った上で、具体的な文献の解読を進めます。予め、担当者を決めて解読した内容を授業内で発表してもらいますが、自分の担当分だけでなく、どの文献も各自で読み、論点を整理し、自分自身の考察を加えることを要請されています。したがって、自分の発表だけでなく、コメンテーターとしても積極的に演習に参加することが期待されます。
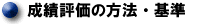
- 学期末ごとのレポート
- 上記レポートだけでなく、授業内の発表担当(年2回くらい)内容も評価の対象になります。

-
授業時に指示します。

-
適宜授業内で指示します。

-
発表者は、少なくとも発表予定日の一週間前には発表テーマ等について、前もって相談した上で、当日は発表レジュメを用意してください。
レジュメの作り方、レポートの書き方などを、ともに学ぶ自主ゼミにも積極的に参加して下さい。


 と有機的な連携をもって、年間の授業内容を構成していきます。この演習と併せて、美術史演習
と有機的な連携をもって、年間の授業内容を構成していきます。この演習と併せて、美術史演習 の受講を期待します。
の受講を期待します。
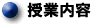


 まとめ
まとめ