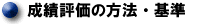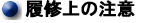| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 高橋 裕子 教授 | 4 | 2 | 通年 | 火 | 1 |

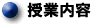
| 1 | イントロダクション |
| 2 | 講義:美術作品への多様なアプローチ(1) |
| 3 | 〃 :美術作品への多様なアプローチ(2) |
| 4 | 〃 :美術作品への多様なアプローチ(3) |
| 5 | 〃 :ディスクリプションの方法/課題:作品ディスクリプション |
| 6 | 〃 :作品比較の方法 |
| 7 | 〃 :美術史の専門文献について/課題:文献探索 |
| 8 | 英語文献講読 |
| 9 | 〃 |
| 10 | 〃 |
| 11 | 〃 |
| 12 | 〃 |
| 13 | モデル発表 |
| 14 | 各人の発表、教員とTAによる講評、質疑応答 |
| 15 | 〃 |
| 16 | 〃 |
| 17 | 〃 |
| 18 | 〃 |
| 19 | 〃 |
| 20 | 〃 |
| 21 | 〃 |
| 22 | 〃 |
| 23 | 〃 |
| 24 | 〃 |
| 25 | 〃 |
| 26 | まとめ、補足など |
| 第1学期には、シラバスに記したもの以外にも、簡単な宿題を何回か出します。 |