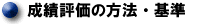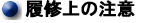| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 高田 博行 教授 | 2 | 3〜4 | 第1学期 | 木 | 3 |

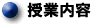
|
取り上げることが可能なテーマには、例えば次のものがある: 1)バイエルン人はどのような発音をするのか。 2)ベルリンとミュンヘンではどのような語彙の違いが見られるのか。 3)ドイツとスイスとオーストリアではどのような文法の違いが見られるのか。 4)女性らしいドイツ語は存在するのか。 5)どんな話し方をすると「上品」、「下品」に響くのか。 6)チャットではどのようなドイツ語が書かれるのか。 7)法律家はどのようなドイツ語を書くのか。 8)政治家はどのようなドイツ語を語るのか。 9)どのような広告文がひとのこころをつかむのか。 10)カフカはどのようなドイツ語を書いたのか。 11)現代でも使われる「古風な」ことばにはどんなものがあるのか。 |