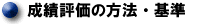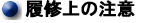| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 小島 紀徳 講師 | 2 | 3 | 第2学期隔週 | 月 月 |
1 2 |

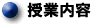
| 1 | 化学工学の概念と装置設計 |
| 2 | 物質・エネルギー収支 |
| 3 | 移動速度論と応用 |
| 4 | 様々な化学プロセス |
| 5 | 公害の歴史と化学工学の寄与 |
| 6 | 化学工学とリサイクル、ごみ問題 |
| 7 | 地球の有限性と地球温暖化問題 |
| 8 | 原因物質と地球の炭素収支 |
| 9 | 二酸化炭素問題とエネルギー |
| 10 | エネルギー利用の現状 |
| 11 | 新エネルギーと資源 |
| 12 | 二酸化炭素問題対策の整理と評価 |
| 13 | 砂漠化と植林、CO2問題 |
| 14 | 自ら課題を申請し、調査結果を発表 |
| 15 | 〃 |
| 1回に2コマずつ7回程度を全授業期間内に実施。なお授業開始を第2週目以降とする場合は休講掲示を行う(休講掲示に注意。掲示がない限り、授業開始後最初の月曜1・2限(予定)から行う)。その後の予定は第一回受講者のみに伝えるが、やむを得ず欠席の場合には、kojima@st.seikei.ac.jpに連絡のこと。 |