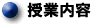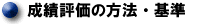●
※日本東洋美術史特殊研究
―近世陶磁における造形的世界を探る―
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
| 荒川 正明 教授 |
4 |
D/M |
通年 |
月 |
3 |

-
空前の経済繁栄を誇った日本の桃山時代。人々は自らの住いや食の空間を飾る素材として、やきものの面白さに注目し始める。畿内に住む数奇者たちを中心に、可塑性のあるやきものの性質を生かして、大胆であり破天荒な造形に果敢に挑んでいく。さらに、江戸時代に入ると九州の肥前窯で磁器の生産が開始される。白い素地があたかもカンバスの役割を演じ、その上に絵画的意匠が展開するのである。近世という時代に全国で展開した魅力ある陶磁の造形世界を探っていきたい。
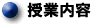
-
| 1 |
オリエンテーション |
| 2 |
中国陶磁からの影響(1) |
| 3 |
中国陶磁からの影響(2) |
| 4 |
『君台観左右帳記』の世界 |
| 5 |
戦国城下町出土の陶磁 |
| 6 |
備前と信楽、伊賀 |
| 7 |
京都のやきもの問屋 |
| 8 |
美濃陶器(1) 瀬戸黒と黄瀬戸 |
| 9 |
美濃陶器(2) 志野と織部 |
| 10 |
肥前磁器(1) 古唐津 |
| 11 |
肥前磁器(2) 唐津 −二彩と象嵌− |
| 12 |
肥前磁器(3) 磁器の誕生−初期伊万里− |
| 13 |
肥前磁器(4) 古九谷様式 |
| 14 |
肥前磁器(5) 古九谷様式 |
| 15 |
肥前磁器(6) 鍋島様式 |
| 16 |
肥前磁器(7) 柿右衛門様式 |
| 17 |
肥前磁器(8) 染付磁器 |
| 18 |
京焼(1) 樂焼 |
| 19 |
京焼(2) 野々村仁清 |
| 20 |
京焼(3) 野々村仁清 |
| 21 |
京焼(4) 尾形乾山 |
| 22 |
京焼(5) 尾形乾山 |
| 23 |
京焼(6) 尾形乾山 |
| 24 |
京焼(7) 江戸後期の作陶家たち |
| 25 |
江戸遺跡出土の陶磁器 |
| 26 |
〃 |

-
スライドを使った講義形式
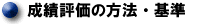
- 第2学期 (学年末試験) :試験を実施する
- 年に数回のレポート
- なるべく実作品に触れるような機会も持ちたい。積極的に授業に参加する学生が望ましい。

-
授業時に指示する

-
荒川正明『やきものの見方』(角川選書)