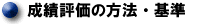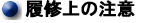| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 保坂 裕興 教授 | 4 | D/M | 通年 | 木 | 6 |

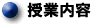
| 1 | オリエンテーション 授業の目的、教科書の使い方、授業の進め方、他の授業科目との関連などについて アーカイブズ学序論(1)アーカイブズ学の構成および用語について |
| 2 | アーカイブズ学序論(2)アーカイブズ学の二大原則と概念モデル(ライフサイクル論とレコード・コンティニュアム論) |
| 3 | アーカイブズ学序論(3)教科書 Keeping Archives (以下、KAとする)による補足 |
| 4 | アーカイブズ学理論の発展(1)アーカイブズのさまざまな活用から方法論へ−メソポタミアからヨーロッパ中世へ、またアジアの諸地域について− |
| 5 | アーカイブズ学理論の発展(2)情報公開と国家・社会−スウェーデンの報道自由法(1766年)− |
| 6 | アーカイブズ学理論の発展(3)フランス革命と市民のアクセス権、およびそれを実現する「フォンド原則」 |
| 7 | アーカイブズ学理論の発展(4)20世紀における世界への拡がり、「記録管理」とライフサイクルの誕生 |
| 8 | アーカイブズ学理論の発展(5)電子記録とインターネットによるパラダイム・チェンジ−コンティニュアムによる新たな挑戦 |
| 9 | アーカイブズ学原論(1)oralityとliterality |
| 10 | アーカイブズ学原論(2)記憶・記録・真実 |
| 11 | アーカイブズ学原論(3)記号学による情報とコミュニケーションの理解 |
| 12 | 教科書 KAによる補足(講読) |
| 13 | 〃 |
| 14 | アーカイブズ制度(1)日本における現状と課題:法制度の観点から |
| 15 | アーカイブズ制度(2)日本における現状と課題:市民活動と企業活動という観点から |
| 16 | アーカイブズ制度(3)世界における現状と課題:ゴール、方策、残された課題 |
| 17 | アーカイブズ制度(4)教科書 KAほかによる補足 |
| 18 | アーカイブズ専門職(1)その歴史と教育・研修 |
| 19 | アーカイブズ専門職(2)アーキビストの倫理規定(Code of Ethics) |
| 20 | アーカイブズ専門職(3)博物館・図書館・アーカイブズの連携−文化遺産の保存活用への貢献 |
| 21 | アーカイブズ専門職(4)教科書 KAほかによる補足 |
| 22 | 普及活動(1)さまざまなコミュニティづくり(教科書 KA 第14章 Advocagy & Outreach)と利用者研究 |
| 23 | 普及活動(2)出版(リーフレット、パンフレット、年報、目録、研究紀要など)の活用 |
| 24 | 普及活動(3)アーカイブズにおける展示活動−業務活動あるいはその成果の展示− |
| 25 | 普及活動(4)補足(講読) |
| 26 | 総括討議および授業のとりまとめ |