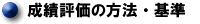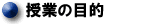
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 家永 遵嗣 教授 | 4 | 2〜4 | 通年 | 月 | 3 |
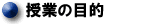
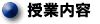
| 1 | 中世日本と東アジア通商圏 日本列島が宋銭を媒介として貨幣経済段階に展開するうえで、北方産物の移入ルートとして東アジア通商圏に組み込まれた側面があること、また、征夷大将軍職が流刑地支配という側面から軍事警察権と辺境支配とを媒介していたということを述べる |
| 2 | 十三湊安藤氏と建武政権・室町幕府 倭人社会とアイヌ(擦文文化人)社会との接点に立っていた十三湊安藤氏と鎌倉幕府・建武政権・室町幕府それぞれとの関係を述べ、室町期社会と北方世界との関係について位置づける |
| 3 | 室町幕府の東国支配 南朝軍との戦争の過程で室町幕府がどのような東国支配を設定したのか、観応の擾乱までの時期を中心に、奥州と関東とに分けて説明する。 |
| 4 | 鎌倉府の東国支配と幕府 観応の擾乱後に関東に設定された「薩埀山体制」と関東の豪族との関係を述べ、小山若犬丸の乱以降の奥州と関東との関係、幕府と鎌倉府との対立関係の形成について述べる。 |
| 5 | 応永の乱と奥州探題の成立 観応の擾乱後の奥州管領乱立状況と、幕府中枢における斯波・細川両氏の対立との関連、鎌倉公方と大内義弘との連繋によって発生した応永の乱が奥州にもたらした影響、特に奥州探題の成立について述べる。 |
| 6 | 十三湊安藤氏と糠部南部氏 十三湊安藤氏が糠部南部氏に敗れて「エゾガ嶋」に逃れる15世紀半ばの事件に焦点を当て、奥州探題大崎斯波氏と篠川公方との対立、大崎斯波氏と幕府中枢との関係について述べる。 |
| 7 | 対馬宗氏と日朝関係 前期倭寇の終息後に形成された李氏朝鮮の対倭人通交政策のなかで対馬宗氏が占めた位置、主家である少弐氏と大内氏との抗争、幕府との関係を調べ、朝鮮王朝との通交関係において要となる対馬宗氏との間に将軍権力が如何なる関係を取り結んでいたかを述べる。 |
| 8 | 足利義教の列島統合戦略と永享の乱 15世紀後期の列島統治に大きな影響を及ぼした幕府の鎌倉府対策の推移を、上杉禅秀の乱から永享の乱に至る時期について調べ、足利義教の構想と、これが足利義政に継承される事情について述べる。 |
| 9 | 嘉吉の乱後の奥州とコシャマインの乱 足利義教の構想から外された形になった篠川御所の滅亡と、足利義教の横死後に幕府が奥州探題を軸にして奥州支配を再建すること、幕府と奥州管領との接続状態、および、十三湊安藤氏がこの体制から排除された形になる事情を調べ、いわゆるコシャマインの乱の背景事情について述べる。 |
| 10 | 関東の社会と享徳の乱 鎌倉時代以来の歴史的経緯によって、関東地方の社会構造が東と西とで相違すること、伝統的な豪族層が生き残り、公方の直臣が配置される東関東と、関東管領の影響下にある西関東との相違を述べ、いったん滅亡した持氏流鎌倉公方家が復活を遂げる社会的な背景、戦国期に継承される社会・政治構造を述べる。 |
| 11 | 堀越公方と幕府政治 享徳の乱によって足利義教の列島統合構想が復活し、古河公方征討政策として確立する事情を述べ、幕府中枢における連携関係、古河公方に替えるために派遣される堀越公方の政治的な構造の特徴を述べる。 |
| 12 | 足利義政の独裁体制と伊勢貞親 無能な将軍として形容されることの多い足利義政だが、政治運営においては極めて専制的で、かつ形式的には最も中央集権的な政治運営を行ったともみなされている。足利義政の政治体制の特徴と、これを支えていた構造的な基礎、独裁的な政治手法の担い手となっていた幕府政所執事伊勢貞親について述べる。 |
| 13 | 伊勢貞親と斯波氏の内紛 伊勢貞親が応仁の乱の原因のひとつとされる斯波氏の内紛に深く関与していた事情を調べ、斯波氏との関係を強めることの政治的な必要性・必然性について、東国対策の観点から検証する。 |
| 14 | 室町幕府−守護体制と将軍独裁 室町幕府−守護体制の発生史を説明し、守護の領国支配を中央集権の観点から位置づける。 |
| 15 | 将軍独裁と守護大名との関係 将軍の独裁が必要とされるに至った事情、将軍の独裁と有力大名との相互依存関係について説明する。 |
| 16 | 有力大名家の分裂と鎌倉府征討政策 足利義教・義政の列島統治構想が将軍権力と有力大名との亀裂を生み出し、有力守護大名家の分裂抗争を引き起こすことを、畠山氏・斯波氏を実例にとって説明する。 |
| 17 | 斯波氏の内紛と足利義視 将軍権力の強圧政策が反対勢力を生み出すことを、西軍諸将の結集という観点から説明する。反発の動きが次期将軍に定められた足利義視を結集点として凝集することを説明する。 |
| 18 | 応仁・文明の乱と古河公方 東西両軍が戦争状態に入ってから一年後、西軍側に古河公方足利成氏と足利義視が参画することにより、西軍は全国的な政治構造としての西幕府の姿をとるにいたる。この将軍独裁の分裂事情を検証する。 |
| 19 | 西軍(西幕府)諸将と古河公方 将軍独裁が生み出した反発が、東幕府・西幕府の力比べの様相を呈するに至った事情を、応仁・文明の乱の終息状況に即して検証する。京都の戦乱の終息が、関東における享徳の乱の終息と連動する事情を述べる。 |
| 20 | 伊勢盛時(北条早雲)の素性 堀越公方を滅ぼして戦国大名となる北条早雲(伊勢盛時)が、実際には足利義政・義尚の側近であり、父である盛定の時代から伊勢貞親直系の将軍独裁のトレーガーであった事情を説明する。 |
| 21 | 日野富子と足利義視との関係 日野富子が足利義視を亡き者にしようとしたことが原因で応仁の乱が始まったという伝承の成立事情を説明し、富子が足利義視の子義稙を義尚の後継将軍候補として強力に推挽した事情を調べて、反証とする。 |
| 22 | 足利政知の子義澄と茶々丸 戦国時代の足利将軍は、堀越公方足利政知の子孫である。政知の子義澄を将軍に擁立する構想の形成事情を、堀越公方と古河公方との関係から検証し、古河公方征討政策の復活という文脈に位置づける。 |
| 23 | 足利義尚の側近伊勢盛時と足利義澄擁立構想 足利義澄を将軍に擁立する構想が、足利義尚の近臣集団側で企画され、伊勢盛時を交渉担当として足利政知とリンクすること、駿河の戦国大名今川氏親の擁立がこの構想の一環であることを述べる。 |
| 24 | 明応二年の政変と戦国期畿内の政治 足利義澄を将軍に擁立する明応二年の政変で戦国期の戦乱が開始される。義澄の擁立者である細川政元政権が畿内の戦国時代を開いた事情について説明する。 |
| 25 | 戦国大名後北条氏と堀越公方 伊勢盛時(北条早雲)が堀越公方足利茶々丸を攻め殺したことが東国の戦国争乱の始まりとされる。早雲と茶々丸の対立事情を明応二年の政変との関係から説明する。あわせて、戦国大名後北条氏家臣団の端緒が堀越公方近臣勢力にあることを説明する。 |
| 26 | 戦国期関東の政治秩序 古河公方と関東管領との連繋によって構成される政治秩序は戦国期関東を強く規定した。古河公方征討政策のトレーガーであった伊勢盛時に始まる戦国大名後北条氏がかかる秩序に融和する政略に転換する事情を調べて、15世紀将軍独裁の列島統治構想の終焉を見定める。 |