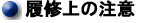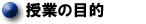
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 家永 遵嗣 教授 | 4 | 2~4 | 通年 | 火 | 1 |
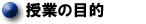
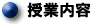
| 1 | 第1学期 「文書」・「記録」・「典籍」の関係、一次史料・二次史料の関係、古文書伝来の事情、様式論・機能論・形態論など古文書学の各分野の概略を説明する |
| 2 | 公式様文書の概略、詔・勅の様式と作成手続き、天皇と太政官との組織的な関係について説明する |
| 3 | 公式様文書のうち符の様式と作成手続き、太政官に関連する事務部門である、弁官・蔵人・外記の役割について説明する |
| 4 | 公式様文書のうち移・牒の様式と使用実態を移式準用の牒に重点を置いて解説する |
| 5 | 公家様文書の概略、および、公家様文書のうちで、当時「宣旨」と総称された内侍宣・口宣・宣旨の様式・使用実態を説明する |
| 6 | 公家様文書のうち、宣旨の展開した形態である官宣旨・国司庁宣・太府宣の様式・使用実態を説明する |
| 7 | 公家様文書のうち、下文について。移式準用の牒および宣旨の発展形態として位置づけ、様式・使用実態を説明する |
| 8 | 公家様文書のうち、書状の一種である奉書の様式的特徴、私文書としての状・啓から書状の形態が発生してくる過程を説明する |
| 9 | 公家様文書のうち、奉書の特殊形態である、院宣・綸旨・女房奉書・伝奏奉書・令旨・摂関家御教書・国宣について説明する |
| 10 | 武家様文書の概略、鎌倉幕府文書のうち、公家様文書との関係が深い、下文・奉書(御教書)について説明する |
| 11 | 鎌倉幕府の生み出した文書様式である、下知状の様式・成立過程・用途を説明する |
| 12 | 例題を用いて演習する |
| 13 | 〃 |
| 14 | 第2学期 室町幕府文書の概略、将軍署判文書の三類型、自判下文・直状・御内書の展開を説明する。また、将軍の直状に関わって、足利直義署判下知状の様式・成立過程・用途について説明する |
| 15 | 室町幕府文書のうち、引付頭人・管領(執事)・奉行人の署判する奉書について説明する。また、幕府の命令書を受けて発行される守護・守護代・守護奉行人などの署判文書を幕府の文書体系と比較して説明する |
| 16 | 戦国大名文書の概略を説明し、印章使用の変遷、印判状について解説する |
| 17 | 解から申状が発生し書状に接近してゆく過程、申状・紛失状について説明する |
| 18 | 請文の発生と二種類の形態、すなわち、報告書としての陳状・使節の請文、職務請負誓約書としての請文、について説明する |
| 19 | 農民の役負担の証書である返抄・請取状、僧侶の役勤仕の証書である巻数請取状について説明する |
| 20 | 武士の軍役負担に関係する証書である覆勘状・着到状・軍忠状について説明する |
| 21 | 祭文・起請・起請文について、宗教意識の変化の動きと関わらせて説明する |
| 22 | 譲状・置文について、相続法制の変化と関わらせて説明する |
| 23 | 売券・借用状について土地所有・貸借関係法制の変化と関わらせて説明する |
| 24 | 例題を用いて演習する |
| 25 | 〃 |
| 授業で提示する古文書は、既に翻刻されたもの(ホンコクと読みます。筆で書かれた文書を現代の活字に置き直したもの)を使用します。史料集に収められている翻刻された古文書から研究上で必要となる情報を得るための基礎的知識を教授します。個々の文書の内容的な読解に関わる訓練は各時代ごとの演習で行われます。 |