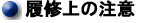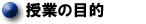
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 家永 遵嗣 教授 | 4 | 2~4 | 通年 | 水 | 2 |
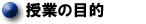
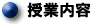
| 1 | 室町時代における武家と公家-日野家・広橋家の位置 義満以降、日野家は代々足利氏の正室を出す姻族となり、広橋家は義満の叔母仲子の縁から足利氏と結びつき、幕府の中枢に参画したイエです。いずれも、持明院統の一流である後光厳天皇の血筋と深い関係にあり、公家と武家とを結びつける役割を果たしていました。その概要を示して、研究の流れのうえで、両家に着目することの意味づけを示します。 |
| 2 | 両統迭立と日野家-①持明院統の近臣としての日野家 鎌倉末期の日野家の人物としては、後醍醐天皇の側近になった資朝が有名ですが、資朝の兄である資名に代表される日野家の主流は持明院統の有力な近臣でした。日野家のおこりから鎌倉末期に至る状況を述べます。 |
| 3 | 両統分裂と日野家-②後醍醐天皇と西園寺公宗室日野名子 日野資名の女子名子は女流日記文学の最後を飾る『竹むきが記』の著者です。建武政権下で中先代の乱の企てに参画し後醍醐天皇の暗殺を試みたもとの「関東申次」西園寺公宗の室となったことが創作の契機でした。建武政権成立前後の日野家の動向を名子の視点から観察します。 |
| 4 | 両統分裂と日野家-③足利政権の成立と西園寺実俊 日野名子の産んだ西園寺実俊は足利政権成立後に幕府と朝廷との交渉を仲介する「武家執奏」の地位につきます。名子の叔父にあたる三宝院賢俊が足利尊氏の挙兵を持明院統に結びつけたことなど、成立期の幕府と日野家との関係を整理します。 |
| 5 | 観応の擾乱と持明院統の分裂-①北畠親房の戦略と西園寺寧子 後醍醐天皇亡き後の南朝を指導した北畠親房は、足利尊氏・直義兄弟の内訌を利用して持明院統の男性皇族を根こそぎ拉致する計画を成功させました。実俊の大叔母にあたる西園寺寧子が幕府の懇請を容れて後光厳天皇を即位させ、持明院統皇統を維持するいっぽうで、持明院統をふたつに分裂させる結果を生じた事情を述べます。 |
| 6 | 観応の擾乱と持明院統の分裂-②崇光流皇統と後光厳流皇統 南朝に拉致された光厳・光明・崇光上皇が帰京するとともに、後光厳天皇と崇光上皇との間に皇位継承を巡る対立が生じた事情を述べます。この対立は、後小松天皇の子である称光天皇で後光厳天皇の血筋が絶えるまで、朝廷政治に深刻な影響を及ぼし続けることを示します。 |
| 7 | 日野宣子と広橋仲子-①足利義満・後円融天皇の出生の秘密 足利義満の生母は後光厳天皇の跡継ぎにあたる後円融天皇の生母広橋仲子と実の姉妹の関係にありました。この血縁関係は名子の同母妹で実俊の室でもあった後光厳天皇の女官日野宣子によって計画的に仕組まれたものであるとみられます。足利義満が後光厳天皇の血筋を庇護する関係を作り出す狙いで設定された関係であったようです。 |
| 8 | 日野宣子と広橋仲子-②後小松天皇の出生と即位 日野宣子は足利義満と日野家との婚姻関係を構築し、義満が崇光上皇の希望を封じて後光厳天皇の皇統を守る立場に立つように人間関係をデザインしたとみられます。日野宣子の布石の全体像を検討します。 |
| 9 | 義満の「家礼(けらい)」になった公家たち-①足利義満の公家化と婚姻関係 日野宣子の画策は、日野家の男性たちを挙げて義満の従者にする形で、日野家のイエのあり方を全体として変容させました。この人間関係が足利義満の公家化現象を発動させる引き金になったとみられることを述べます。 |
| 10 | 義満の「家礼」になった公家たち-②公家社会全体の変容 足利義満の公家化現象は公家社会全体に反応を引き起こして、その様相を著しく変容させました。義満の武力的な圧力による現象ではなく、公家社会の側が積極的に足利義満に追従して臣従するという点に特徴があります。その様相を観察して、その意味を考えます。 |
| 11 | 足利義満「皇位窺覦」説とその根拠 近代の公武関係理解の背景には、尊王攘夷論を経由して成立した「公武対立」論が存在します。足利義満が皇位簒奪を図ったとする「皇位窺覦」説もそのひとつで、現在でも非常に強い影響力を保っています。その根拠とされた事象を検討します。 |
| 12 | 「北山殿」広橋仲子と「北山殿」足利義満 足利義満が後小松天皇から皇位を奪うつもりであったのかなかったのかという問題は、日常的な家族の接触というリアリティに照らして検証してみる余地があります。義満の北山御所、のちに金閣の鹿苑寺になるものは、「北山殿」と呼ばれていた叔母広橋仲子(崇賢門院)の御所の隣に義満が引っ越す形で成立したもので、引っ越しののちには義満が「北山殿」と呼ばれるようになりました。義満と後小松天皇の祖母広橋仲子との日常的なつきあいの様相を観察してみます。 |
| 13 | 鎌倉期公家政権と伝奏・内裏「小番」 足利義満以降、「伝奏」という地位が朝幕交渉の要になり、江戸時代末まで続くことになります。義満が後小松天皇の身辺警護のために公家衆に課した警固任務である禁裏「小番」「小番衆」も、近世公家が幕府から所領を給与されるうえでの根拠として江戸時代末まで維持されることになります。伝奏・内裏「小番」がどのように成立したのかを振り返ります。 |
| 14 | 伝奏奉書と「公武統一政権」論-①武家執奏から伝奏へ 鎌倉時代の「関東申次」の系譜をひき、14世紀の朝幕交渉の仲立ちであった「武家執奏」の地位が、足利義満の公家化現象を契機として消滅してしまうことを検討し、「伝奏」への移行についてこれまでどのように考えられてきたのかを検証します。 |
| 15 | 伝奏奉書と「公武統一政権」論-②公家主導か武家主導か 足利義満が皇位簒奪を狙っていたのかどうかは別として、義満や周囲に仕えている人間たちが義満を上皇(法皇)だと心得ていたことはおおよそ間違いないようです。確実な証拠として、上皇の取り次ぎ役である「伝奏」が義満の命令を下達しているという事実が注目されてきました。とはいえ、この事実をどのように解釈するのかということについては見解が一致していない実情です。実態と評価について、これまで戦わされてきた議論を検討してみます。 |
| 16 | 伝奏奉書と「公武統一政権」論-③「家礼」という観点の導入 朝廷の役職である伝奏が武家の命令を下達するという現象には変化があるようです。「伝奏として」その命令を伝えたと言うことは必ずしも簡単には言えない、「伝奏である」者が「義満の従者として」義満の命を下達したケース、「伝奏ではない義満の従者」が伝奏の場合と同じように義満の命を下達したケース、があるからです。その人物の帯びている関係性の構造に変化があるということのようです。この事情を、変化の様相が明瞭に割り出せる南都伝奏を例にとって検討してみます。 |
| 17 | 後光厳院流皇統の断絶-①足利義持・後小松上皇にとっての危機 義満没後、又従兄弟の関係にあった足利義持と後小松上皇は協調関係を構築します。二人は男子に恵まれないという共通の悩みを抱えており、両統迭立の実現を求める後南朝勢力、足利氏家督の地位を窺う鎌倉公方足利持氏、という共通する敵対者に直面していたのです。特に足利義持の晩年に深刻化したこの危機の様相を検証します。 |
| 18 | 後光厳院流皇統の断絶-②正親町三条家と伏見宮家 義持晩年の危機は、弟である足利義教の将軍職襲職、後光厳流皇統から崇光流皇統への皇統の転換という形で突破が図られました。後光厳流皇統を護持してきた日野家が義教の正室の座を失い、正親町三条家がこれに代わることになります。正親町三条家が14世紀から武家と崇光流皇統(伏見宮家)と親しい関係にあったことを述べます。 |
| 19 | 足利義教の恐怖政治と日野家の没落 足利義教の将軍職襲職から間もなく、崇光天皇が亡くなって後光厳流皇統は実質的に断絶します。伏見宮家から後小松天皇の要旨に迎えられた後花園天皇が皇位について建前の上では皇統の変化はなかった建前とされますが、実態としての人間関係の親疎はありろ、何の影響も生じないということはありえません。足利義教時代は非常に多くの公家衆が弾圧されて地位を失います。後光厳流皇統を護持してきた日野家が義教の正室の座を逐われ、実質的に絶家に追い込まれることを検討します。 |
| 20 | 日野家の復活-①日野重子と足利義勝・義政兄弟 いったん絶家に追い込まれた日野家(日野裏松家)が復活できたきっかけは、足利義教の横死にあります。日野裏松重子の産んだ義勝・義政が将軍職についたことを背景として、重子の甥日野勝光を中心として日野裏松家が再興されることを述べます。 |
| 21 | 日野家の復活-②日野勝光・富子・良子兄妹 日野裏松家の再興は、後花園天皇が後土御門天皇に譲位した文正元(1466)年に勝光が院執権となった頃におおよそ達成されました。勝光は同母姉妹にあたる足利義政の正室日野富子・義視の正室良子を介して幕府に対しても大きな影響力があったことを述べます。 |
| 22 | 日野富子の謎-①足利義視はなぜ将軍職後継者になったか 足利義視は正親町三条家ゆかりの人物で、日野勝光・富子らとの関係はがんらい乏しい。日野勝光が栄達を遂げた時期に足利義視が義政の後継者に定められたことの意味を検討します。この観点から、日野富子の同母妹良子が義視の正室になる事情を、正親町三条家との関係を考慮して検討します。 |
| 23 | 日野富子の謎-②山名宗全との関係 軍記『応仁記』によれば、日野富子は山名宗全を焚きつけて足利義視を亡き者にしようと図ったと伝えられています。しかし、宗全は義視と親しかったとみるべきで、富子も良子との関係から義視と親しかったと考えられます。大乱中の勝光・富子の動向を朝廷を視野に入れて説明します。 |
| 24 | 足利義視の謎-③日野富子と明応二年の政変 明応二年の政変は戦国争乱の本格的な始まりを告げる動乱の糸口になった事件です。日野富子は自分が将軍職に擁立した義視の子足利義材を廃立する政変に積極的に荷担したとみられます。富子の変心の原因を検討します。 |
| 25 | 室町時代における武家と公家 対立か協調か、その基調を捉えるための着目点についてまとめます。 |