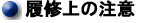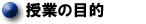
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 家永 遵嗣 教授 | 4 | D/M | 通年 | 月 | 4 |
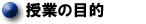
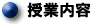
| 1 | 参加者の自己紹介の上で発表順序を決定します。 |
| 2 | 後小松天皇即位の周辺事情について、2回にわたり教員からのレクチュアを行います。最初は、後小松天皇即位の周辺事情について、政治史的な観点から大局観と論点を指摘します。 |
| 3 | 日野宣子と日野一門の動向、崇賢門院広橋仲子と宣子との関係、仲子と足利義満との関係、日野宣子と並んで重要な二条良基の挙動についてレクチュアします。 |
| 4 | 以後、決定された発表順序に従って講読・論議をすすめます。 |
| 桃崎氏の翻刻に従い、永徳元年九月二二日条から講読する。 |