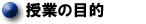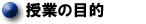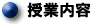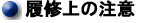| 1 |
演劇学に関するオリエンテーションI |
| 2 |
演劇学に関するオリエンテーションII |
| 3 |
Aufführungの概念I |
| 4 |
Aufführungの概念II |
| 5 |
Aufführungsanalyse I |
| 6 |
Aufführungsanalyse II ――『エミーリア・ガロッティ』の演出を例に |
| 7 |
Aufführungsanalyse III ――『エミーリア・ガロッティ』の演出を例に |
| 8 |
Theaterhistoriografie I |
| 9 |
Theaterhistoriografie II |
| 10 |
Theoriebildung I |
| 11 |
Theoriebildung II |
| 12 |
文化のAufführung I |
| 13 |
文化のAufführung II |
| 14 |
InszenierungとAufführung |
| 15 |
第一学期の総括 |
| 16 |
上演分析と「演出演劇」に関するオリエンテーション |
| 17 |
(以下は順不同です)シラー作、ニコラス・シュテーマン演出:群盗 |
| 18 |
シラー作、アンドレア・ブレート演出:ドン・カルロス |
| 19 |
ゲーテ作、クラウス・ミヒャエル・グリューバー演出:ファウスト第一部 |
| 20 |
ゲーテ作、クリストフ・マルターラー演出:ファウスト第一部 |
| 21 |
クライスト作、ペーター・シュタイン演出:公子ホンブルク |
| 22 |
ハウプトマン作、ヴァレンティン・イェーカー演出:ローザ・ベルント |
| 23 |
シュニッツラー作、ミヒャエル・タールハイマー演出:恋愛三昧 |
| 24 |
ホルヴァート作、クリストフ・マルターラー演出:カジミールとカロリーネ |
| 25 |
ツックマイアー作、カタリーナ・タールバッハ演出:ケーペニックの大尉 |
| 26 |
ブレヒト作、ハイナー・ミュラー演出:アルトゥロ・ウイ |
| 27 |
ミュラー作、ロバート・ウィルソン演出:ハムレットマシーン |
| 28 |
ベルンハルト作、クラウス・パイマン演出:座長ブルスコン |
| 29 |
イェリネク作、ヨシ・ヴィーラー演出:雲。家 |
| 30 |
第二学期の総括 |