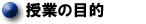
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 長佐古 真也 講師 | 4 | 2~4 | 通年 | 土 | 1 |
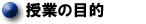
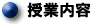
| 1 | ガイダンス |
| 2 | 「民俗」とは/「民俗」にふれる |
| 3 | 「民俗」とは/私たちは、古いしきたりとは無縁か |
| 4 | 「民俗」とは/自らを見つめる視点 |
| 5 | 「民俗」とは/柳田國男という人 |
| 6 | 「民俗」とは/歴史学としての民俗学 |
| 7 | 普段使いの食器から/なぜ、「ご飯茶碗」なのか? |
| 8 | 普段使いの食器から/普段使いのワンの歴史 |
| 9 | 普段使いの食器から/身の回りの「史料」達 |
| 10 | 普段使いの食器から/有形民俗の調査法等について |
| 11 | 「あの世」のご時世/お葬式を考える |
| 12 | 「あの世」のご時世/様々な葬送儀礼(1) |
| 13 | 「あの世」のご時世/様々な葬送儀礼(2) |
| 14 | 「あの世」のご時世/お墓は未来永劫に残るものか? |
| 15 | 「あの世」のご時世/お葬式・お墓の歴史(1) |
| 16 | 「あの世」のご時世/お葬式・お墓の歴史(2) |
| 17 | 「あの世」のご時世/「イエ」・「ムラ」、もしくは「家族」・「地域」 |
| 18 | 「民俗」の今/現代の「民具」とは何か |
| 19 | 「民俗」の今/渋沢敬三という人 |
| 20 | 「民俗」の今/「少し前の暮らし」を残す枠組み |
| 21 | 「民俗」の今/今を語る史料としての「もの」 |
| 22 | 「民俗」の今/「民藝」という運動 |
| 23 | 民俗学の広がり、そして学際へ |
| 24 | 民俗学を使うということ |
| 授業の進捗の都合で、内容が変わったり、順序が入れ替わることがあります。 |



