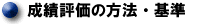| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 第1学期 山本 成生 講師 第2学期 豊永 聡美 講師 |
4 | 通年 | 火 | 1 |

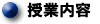
| 1 | イントロダクション――「音楽」とは何か、「音楽史」とは何か |
| 2 | 「バロック時代」の音楽と社会 |
| 3 | 通奏低音からソナタ形式へ――バロックから古典派への移行 |
| 4 | 「古典派」音楽の諸特徴 |
| 5 | 音楽家と「パトロン」 |
| 6 | 市民革命と古典主義の終焉 |
| 7 | 「ロマン派」音楽の諸特徴1 |
| 8 | 音楽における「ロマン主義」 |
| 9 | 音楽はどこで演奏されたか――劇場・サロン・家庭 |
| 10 | 「ロマン派」音楽の諸特徴2 |
| 11 | 巨大化するオーケストラと「聴衆の誕生」 |
| 12 | 楽器が生んだヴィルトゥオーゾ――楽器産業の展開 |
| 13 | 音楽の政治的・社会的諸機能 |
| 14 | 「歴史」となった音楽――音楽評論・万国博覧会・音楽学 |
| 15 | まとめ |

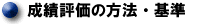


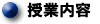
| 1 | イントロダクション 日本音楽史の全体像 |
| 2 | 日本の楽器の源流 |
| 3 | 日本の音楽の源流 |
| 4 | 雅楽の編成と演奏形態 |
| 5 | 正倉院の楽器と東大寺大仏開眼供養会 |
| 6 | 伎楽と東アジアの世界 |
| 7 | 宮廷社会における音楽 |
| 8 | 源氏物語の音楽 |
| 9 | 法会と仏教音楽 |
| 10 | 祭祀と御神楽 |
| 11 | 能楽の歴史 |
| 12 | 能の鑑賞 ―談山神社「翁」奉納― |
| 13 | 近世邦楽のあけぼの |
| 14 | 歌舞伎と音楽 |
| 15 | 総括 |