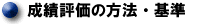| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 平田 栄一朗 講師 | 4 | 3~4 | 通年 | 金 | 3 |

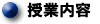
|
第一学期は、上記書“Methoden der Tanzwissenschaft“に収録されている論考(15本)を少しずつ読み進めていきます。担当箇所(10‐15ページ程度)をあらかじめ決めて、担当者が30分程度の発表を行い、その後、参加者同士で質疑応答や意見交換を行います。どの論考を取り上げるかについては、授業開始後の早い段階で相談して決めたいと思います。 第二学期の授業ではまず邦訳文献『パフォーマンス美学』や、パフォーマンス研究に関する日本語文献を読み(授業3回程度)、その後は「授業の目的」に記した文献のパフォーマンス論を取り上げていきます。第一学期と同様、担当箇所をあらかじめ決めて、担当者の発表、その後質疑応答・意見交換を行います。授業参加者の関心領域を出来るだけ反映した論を扱いますので、取り上げたいパフォーマンス理論について早めに授業担当者とご相談ください。 |