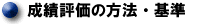| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 天利 浩 講師 | 4 | 2~4 | 通年 | 月 | 2 |

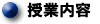
| 1 | 財政学とは、政府の役割 |
| 2 | 政府の規模、所得再分配機能 |
| 3 | 市場の失敗 |
| 4 | 財政の仕組み:日本の財政制度(1)予算制度 |
| 5 | 財政の仕組み:日本の財政制度(2)日本財政の現状、財政投融資 |
| 6 | 経済分析の基本:限界概念、需要曲線、供給曲線 |
| 7 | 経済分析の基本とその応用:余剰分析 |
| 8 | 市場と効率性 |
| 9 | 外部性(1)ピグー税 |
| 10 | 外部性(2)コースの定理 |
| 11 | 公共財(1)公共財の性質、公共財の最適供給 |
| 12 | 公共財(2)リンダール均衡 |
| 13 | 中位投票者定理 |
| 14 | 自然独占と料金設定 |
| 15 | 理解度の確認 |
| 16 | マクロ経済学の基本:GDP、消費、投資 |
| 17 | 景気安定化機能 |
| 18 | ミクロ経済分析の基本:無差別曲線、最適消費 |
| 19 | 所得効果と代替効果、死重損失 |
| 20 | 租税の基礎理論 |
| 21 | 課税ベースの選択:所得課税と消費課税 |
| 22 | 労働所得税の効果 |
| 23 | 個別物品税の効果 |
| 24 | 利子所得税の効果、資産に対する課税 |
| 25 | 財政収支 |
| 26 | 財政の持続可能性と財政再建 |
| 27 | 公債の負担 |
| 28 | 公的年金 |
| 29 | 地方財政 |
| 30 | 理解度の確認 |
| 経済学を理解していただくために、基本的な経済学から講義を開始します。この講義において、経済学は、財政学を理解するための道具なので、経済学を完璧に理解するよりも、経済学の基礎をしっかりと理解した上で、財政全般について偏りのない視点を持つ方が重要です。 |