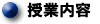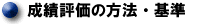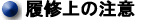| 1 |
開講の辞/授業の進め方の説明/取り上げる判例の割り当て |
| 2 |
具体例で事案の要約をやってみる:①最判昭35.3.18民集14-4-483(営業許可のない食肉販売の効力) |
| 3 |
②最判昭39.1.23民集18-1-37(有毒あられ混入事件) |
| 4 |
③最判昭36.12.15民集15-11-2852(不特定物売買における瑕疵ある物の給付) |
| 5 |
④最判平13.11.27民集55-6-1311(566条3項の1年の期間と消滅時効との関係) |
| 6 |
⑤大判昭10.10.5民集14-1965(宇奈月温泉事件) |
| 7 |
⑥最判昭43.9.3民集22-9-1767(対抗力なき借地人の保護) |
| 8 |
⑦最判昭45.12.11民集24-13-2015(612条2項の解除権の制限) |
| 9 |
⑧最判昭44.7.4民集23-8-1347(非営利法人の目的の範囲) |
| 10 |
⑨最判昭62.12.15民集41-1-1(女児の逸失利益の算定) |
| 11 |
⑩最判昭56.1.19民集35-1-1(651条の解除権の制限) |
| 12 |
⑪最判昭36.11.30民集15-10-2629(事務管理を根拠に法定代理権を認めることはできるか) |
| 13 |
⑫最判昭44.4.25民集23-4-904(背信的悪意者排除) |
| 14 |
⑬最判平8.10.29民集50-9-2506(背信的悪意者からの転得者の保護) |
| 15 |
⑭最判昭45.9.22民集24-10-1424(94条2項類推適用)/まとめ(事案の要約のしかた) |
| 16 |
⑮最判平10.2.13民集52-1-65(未登記通行地役権の対抗力) |
| 17 |
⑯最判昭49.9.26民集28-6-1213(96条3項の善意の第三者と対抗要件具備の必要性) |
| 18 |
⑰最判昭38.2.22民集17-1-235(共同相続と登記) |
| 19 |
⑱最判昭37.6.22民集16-7-1374(明認方法の対抗力--立木の二重譲渡) |
| 20 |
⑲最判昭29.8.31民集8-8-1567(寄託動産の譲渡と対抗要件) |
| 21 |
⑳最判平12.6.27民集54-5-1737(盗品の取得) |
| 22 |
㉑最判昭34.7.14民集13-7-960(自治体の長の行為と110条類推適用) |
| 23 |
㉒最判昭42.4.20民集21-3-697(代理人の権限濫用) |
| 24 |
㉓最判昭46.4.20家月24-2-106(親権者と子の利益相反) |
| 25 |
㉔最判昭62.7.7民集41-5-1133(無権代理人の責任) |
| 26 |
㉕最判平5.1.21民集47-1-265(無権代理人が本人を共同相続をした場合の無権代理行為の効力) |
| 27 |
㉖最判昭36.2.16民集15-2-244(梅毒輸血事件:医療機関の注意義務) |
| 28 |
㉗最判昭45.7.16民集24-7-909(転用物訴権1) |
| 29 |
㉘最判平7.9.19民集49-8-2805(転用物訴権2) |
| 30 |
まとめ |