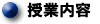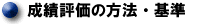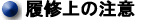| 1 |
導入 |
| 2 |
日本の法学方法論・入門 |
| 3 |
法と経済学入門 |
| 4 |
事前(ex ante)と事後(ex post)(1)概観 |
| 5 |
事前(ex ante)と事後(ex post)(2)事例の理解 |
| 6 |
事前(ex ante)と事後(ex post)(3)分析手法の理解・評価 |
| 7 |
効率性(efficiency)(1)概観 |
| 8 |
効率性(efficiency)(2)事例の理解 |
| 9 |
効率性(efficiency)(3)分析手法の理解・評価 |
| 10 |
限界(margin)分析(1)概観 |
| 11 |
限界(margin)分析(2)事例の理解 |
| 12 |
限界(margin)分析(3)分析手法の理解・評価 |
| 13 |
単独所有者(single owner)論(1)概観 |
| 14 |
単独所有者(single owner)論(2)事例の理解 |
| 15 |
単独所有者(single owner)論(3)分析手法の理解 |
| 16 |
最安価費用回避者(least cost avoider)(1)概観 |
| 17 |
最安価費用回避者(least cost avoider)(2)事例の理解 |
| 18 |
最安価費用回避者(least cost avoider)(3)分析手法の理解・評価 |
| 19 |
管理費用(administrative cost)(1)概観 |
| 20 |
管理費用(administrative cost)(2)事例の理解 |
| 21 |
管理費用(administrative cost)(3)分析手法の理解・評価 |
| 22 |
レントシーキング(1)概観 |
| 23 |
レントシーキング(2)事例の理解 |
| 24 |
レントシーキング(3)分析手法の理解・評価 |
| 25 |
コースの定理(1)概観 |
| 26 |
コースの定理(2)事例の理解 |
| 27 |
コースの定理(3)分析手法の理解・評価 |
| 28 |
分析手法のまとめ |
| 29 |
日本における議論状況 |
| 30 |
総括 |