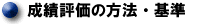| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 三平 正明 講師 | 4 | 1~4 | 通年 | 水 | 2 |

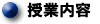
| 1 | 論理学とは? |
| 2 | 人工言語を作ろう!:自然言語から形式言語へ |
| 3 | この言語の意味論:論理結合子の意味と真理表 |
| 4 | 恒真式と矛盾式 |
| 5 | 論理的同値、同値変形 |
| 6 | 論証の妥当性 |
| 7 | 自然演繹の方法とは? |
| 8 | 自然演繹 |
| 9 | 〃 |
| 10 | 練習問題を解こう! |
| 11 | メタ論理:自然演繹の方法は信頼できるか? |
| 12 | 健全性と完全性 |
| 13 | 命題論理から述語論理へ:命題論理の限界、文の内部構造を分析する必要性 |
| 14 | 名前と述語、変項と量化子、ヴェン図 |
| 15 | まとめ |
| 16 | 関係表現、多重量化 |
| 17 | 述語論理の言語とその意味論 |
| 18 | 解釈という方法 |
| 19 | 妥当式と矛盾式 |
| 20 | 論証の妥当性 |
| 21 | 自然演繹の方法を拡張する |
| 22 | 量化子の推論規則(1) |
| 23 | 量化子の推論規則(2) |
| 24 | 同一性:等号の推論規則 |
| 25 | 練習問題を解こう! |
| 26 | メタ論理:自然演繹の方法は信頼できるか? |
| 27 | 健全性と完全性 |
| 28 | 確定記述 |
| 29 | 理解度の確認 |
| 30 | 予備日 |
| この授業では、特別な予備知識は何も必要としない。履修者に求められているのは、実際に手を動かして日本語の文を形式言語に翻訳したり、真理表や証明図を作成したりすることだけである。 |