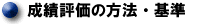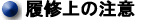| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 高橋 朋子 講師 | 4 | 2~4 | 通年 | 木 | 5 |

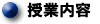
| 1 | 論文の書き方 -方法と実践ー(講義) |
| 2 | 論文を読むこと、理解すること (講義) |
| 3 | 論文を発表すること (講義) |
| 4 | 文献講読と解説 |
| 5 | 〃 |
| 6 | 〃 |
| 7 | 〃 |
| 8 | 〃 |
| 9 | 〃 |
| 10 | 〃 |
| 11 | 〃 |
| 12 | 〃 |
| 13 | 〃 |
| 14 | 理解度の確認、まとめ。4年生はこの時までに卒業論文のテーマを、3年生はこの時までに第2学期の発表のテーマを提出すること。 |
| 15 | 予備日 |
| 16 | まず4年生から順次各自の発表。4年生が終了次第、3年生の発表となる。 全員での質疑応答 |
| 17 | 〃 |
| 18 | 〃 |
| 19 | 〃 |
| 20 | 〃 |
| 21 | 〃 |
| 22 | 〃 |
| 23 | 〃 |
| 24 | 〃 |
| 25 | 〃 |
| 26 | 〃 |
| 27 | 〃 |
| 28 | 〃 |
| 29 | 本年度の総括 |
| 30 | 予備日 |
| この授業では発表者のみが授業の参加者ではなく、聴く側もまた積極的に毎回授業に参加することを求めます。発表はよき質問によってさらに内容を向上させることができるし、また的確に質問できるということは、しっかりとした論文を書くための第1歩です。従って全員が質問者になるように計らう予定です。 |