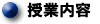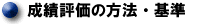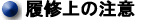●
日本文学史概説Ⅲ
―メディアの中の文学史―
| 担 当 者 |
単 位 数 |
配当年次 |
学 期 |
曜 日 |
時 限 |
| 中山 昭彦 教授 |
4 |
1~4 |
通年 |
水 |
3 |

-
文学作品は単に文字として書かれただけでは成立しない。木版から活版への印刷技術の変容や挿絵などの図像の役割の変化、雑誌新聞などの発表媒体の中での位置づけの変容など、そこには実にさまざまな要素が折り重なっている。つまり文学作品そのものが読者に何かを伝えるメディアであると同時に、写真、図像、新聞、雑誌、書物といった他のメディアが干渉し、それらと交錯することによって文学作品ははじめて成立するのだともいえる。また作家の写真や個人的な情報などによって形成される作家のイメージも、文学作品を成立させるメディアのひとつと考えることができるだろう。
この授業では主に1890年代〜1920年代を対象に、メディア別に文学作品との様々な関係を辿り、他のメディアと交錯することで、文学作品の読み方や意味がどのように変わってゆくのかを歴史的に考えてみたい。
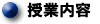
-
| 1 |
授業の概要・ガイダンス |
| 2 |
印刷技術と読書形態 |
| 3 |
〃 |
| 4 |
〃 |
| 5 |
〃 |
| 6 |
〃 |
| 7 |
〃 |
| 8 |
〃 |
| 9 |
本の形態と作品という単位 |
| 10 |
〃 |
| 11 |
〃 |
| 12 |
〃 |
| 13 |
〃 |
| 14 |
第1学期の授業のまとめ |
| 15 |
自主研究 |
| 16 |
新聞雑誌における作家の写真の役割 |
| 17 |
〃 |
| 18 |
〃 |
| 19 |
〃 |
| 20 |
〃 |
| 21 |
新聞雑誌における作家の個人情報の役割 |
| 22 |
〃 |
| 23 |
〃 |
| 24 |
〃 |
| 25 |
〃 |
| 26 |
挿絵の役割の変遷 |
| 27 |
〃 |
| 28 |
〃 |
| 29 |
第2学期の授業のまとめ |
| 30 |
自主研究 |

-
基本的には講義形式で行う。ただし、授業内容の理解を確実なものにし、資料を精密に読解した上で粘り強く分析と考察を行う能力を養うため、授業中に配布した資料を分析し、その結果をレポートしてもらうことがある。また、次回までに配布した資料や文学作品を熟読して来てもらい、それを前提として授業を行う場合がある。なお、上の「授業内容」で示したメディア別のテーマは、授業の進展具合に応じて、順番を入れ替えることも考えている。
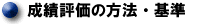
- 第2学期 (学年末試験) :試験を実施する
- 第1学期に課すレポートと第2学期の学年末試験が成績評価の主な要素である。これに授業中に課す小レポートと小テスト、出席などの平常点を加味して評価する。

-
紅野謙介『書物の近代』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、1999年
教科書以外に多くの資料を配付する予定。

-
ロジェ・シャルチエ『書物の近代』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、1996年
永嶺重敏『〈読書国民〉の誕生』日本エディタースクール出版部、2004年
ベネディクト・アンダーソン『増補想像の共同体』NTT出版、1997年
山本芳明『文学者はつくられる』ひつじ書房、2000年
金子明雄他『ディスクールの帝国』新曜社、2000年
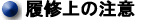
- 第1回目の授業に必ず出席のこと。