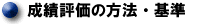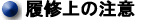| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 光野 正幸 講師 | 2 | 1~4 | 第2学期 | 金 | 4 |

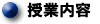
| 1 | イントロダクション ~ウィーンの「世紀末」とグスタフ・マーラー~ |
| 2 | 音楽史的序説(1)~ジャンルとしての「交響曲 Symphonie」の発展~ |
| 3 | 音楽史的序説(2)~ジャンルとしての「ドイツ・リート」の発展~ |
| 4 | マーラーの作品(1)~『嘆きの歌』(初稿1880)~ |
| 5 | マーラーの作品(2)~交響曲第一番「巨人」~ |
| 6 | マーラーの作品(3)~歌曲集『子供の魔法の角笛』より~ |
| 7 | マーラーの作品(4)~交響曲第二番「復活」~ |
| 8 | マーラーの作品(5)~交響曲第三番・第四番「大いなる喜びへの賛歌」~ |
| 9 | マーラーの作品(6)~交響曲第五番・第六番「悲劇的」~ |
| 10 | マーラーの作品(7)~交響曲第七番「夜の歌」~ |
| 11 | マーラーの作品(8)~交響曲第八番「千人」~ |
| 12 | マーラーの作品(9)~『大地の歌』~ |
| 13 | マーラーの作品(10)~交響曲第九番~ |
| 14 | 全体の総括 ~音楽史上のマーラーの意義: リヒャルト・シュトラウス、新ウィーン楽派とマーラー~ |
| 15 | 理解度の確認 |
| 作曲家グスタフ・マーラーを題材に採りあげる以上、クラシック音楽の話題が中心になるのは当然のことだが、話はしばしば文学、思想、美術にも、また文化政策一般にまでも「飛び火」する筈で、いわば文化史研究のケース・スタディとしての「マーラー論」を展開する予定。 |