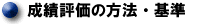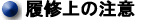| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 石井 菊次郎 教授 岩田 耕一 教授 河野 淳也 准教授 髙屋 智久 助教 仲山 英之 助教 宮内 直弥 助教 |
6 | 3 | 第2学期 | 火、水、木 | 3、4、5 |

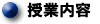
|
約12週間にわたって下記のテーマのうちから8テーマの実験を行う。最初に行うテーマについては2週間実験し、その結果について口頭発表を行う。また、学期最後の3週間は、レポートの添削・討論および補習実験にあてる。 X線回折、赤外吸収スペクトル、エレクトロニクス、凝固点降下、溶解熱、気体の粘性率、磁性、電気化学、真空と電子、吸着、反応速度、光化学 |