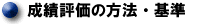| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 小川 束 講師 | 2 | 2 | 集中(第2学期) |

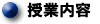
| 1 | 日本の数学史を概観します。 |
| 2 | 建部賢弘(たけべかたひろ)の『綴術算経(てつじゅつさんけい)』にある円周率の計算を紹介します。 |
| 3 | なぜ建部賢弘は円周率の計算をしたのか、その歴史的背景を探ります。 |
| 4 | リチャードソン補外について復習をして、建部賢弘の計算の本質を検討します。 |
| 5 | 建部賢弘の円弧の長さの計算を紹介します。 |
| 6 | 建部以降の円周率計算はどのように展開したのか、安島直円(あじまなおのぶ)の『弧背術解』を読んでみます。 |
| 7 | 安島直円の円周率計算について考察します。 |
| 8 | 安島直円が用いた二項展開について補足をします。 |
| 9 | ホイヘンスのDe Circuli Magnitudine Inventa(円の大きさの発見)にある円周率の計算を紹介します。 |
| 10 | ヨーロッパと日本の数学観を比較検討して、それぞれの数学の特質を探ります。 |
| 11 | 建部賢弘の『綴術算経』の「自質の説」を読んで建部の数学観、数学者観を読み解きます。 |
| 12 | 明治時代における西洋数学の導入について講義します。 |
| 13 | 数学史の研究の最前線を紹介します。 |
| 14 | 全体のまとめをします。 |
| 15 | 予備日 |
| 数学を学ぶ際の励ましとなるような、また卒業後就職しようと考えている上級生には15年以上も学んだ数学とは一体何だったのか振り返ってもらえるような、さらに大学院へ進学をしようと考えている人には勇気と決意を新たにできるような講義にしたいと考えています。 |