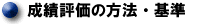| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 大岩 烈 講師 | 2 | D/M | 第2学期 | 月 | 2 |

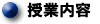
| 1 | 表面・界面分析の概要と実際の応用例 |
| 2 | 固体とX線、電子、イオンの相互作用 |
| 3 | 電子、X線、イオンの発生 |
| 4 | 超高真空技術と表面分析 |
| 5 | 表面分析の原理(1)電子を使った分析手法-1 |
| 6 | 表面分析の原理(1) 電子を使った分析手法-2 |
| 7 | 表面分析の原理(1) 電子を使った分析手法-3 |
| 8 | 表面分析の原理(2)X線を使った分析手法-1 |
| 9 | 表面分析の原理(2)X線を使った分析手法-2 |
| 10 | 表面分析の原理(3)イオンを使った分析手法 |
| 11 | 微小領域分析の最前線 |
| 12 | 各種表面分析の半導体プロセスへの応用 |
| 13 | 各種表面分析の有機材料への応用 |
| 14 | まとめ |
| 15 | 予備日 |
| 日本の優れた産業技術は、長い年月の蓄積から生まれる基礎科学に基づいた材料開発力に支えられてきた。それを支えてきたのが材料評価技術である。ナノテクノロジー技術を駆使したスマートフォン、デジタル家電や燃料電池に代表されるように21世紀の産業の糧は、如何にして材料の表面・界面を制御して必要とする機能を発現させるかにある。表面評価技術は、固体に電子線、X線やイオンを照射し、固体との相互作用によって発生する電子、イオン等の信号を検出、解析して表面の組成や構造を推定する方法である。本講義では、代表的な表面・界面の評価手法の基礎と応用を豊富な具体例を挙げて解説する。 |