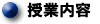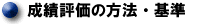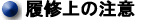| 1 |
学びの経験としてのカリキュラム。「カリキュラム」の概念は「学びの経験の総体」として定義されている。この「学びの経験」の意味を解説し、「学びの経験」と「学力」との関係について講述する。 |
| 2 |
学力とは何か。学力の概念について、さまざまな定義を紹介し、学力の評価を確実にし、学力をめぐる議論を確かなものにするための作業的定義を示す。 |
| 3 |
学力問題とは何か。いわゆる「学力問題」の議論を今日の時点で整理し、「学力問題」の語られ方がどのように推移し、何が問題として残されたのかについて検証する。 |
| 4 |
日本の学力の特徴。OECDのPISA調査の結果、および、IEAのTIMS調査の結果を示し、国際学力調査に現れた日本の学力の特徴について解説する。 |
| 5 |
学力調査による国際比較。国際学力調査の結果から、世界各国の学力問題の現れを北米、ヨーロッパ、アジアの三つの地域で比較し、グローバリゼーションの中の学力問題の再解釈を試みる。併せて高位の学力を獲得した国の教育についても紹介する。 |
| 6 |
学びからの逃走。学力低下の一つの要因として「学びからの逃走」の現象がある。なぜ、日本の子どもを含む東アジア諸国の子どもは学びから逃走するのか。その実態を実証的なデータによって提示する。 |
| 7 |
東アジア型教育の混迷。「学びからの逃走」は東アジア諸国に共通した特徴であり、それ自体が東アジア型教育の破綻を示している。その要因と歴史的背景を提示し、この地域における学びの質と学びの様式を変革する試みを紹介する。 |
| 8 |
学びの再定義。「勉強」から「学び」への転換を達成するために、学びの再定義を行う。学びは「出会いと対話」による「意味と関係の編み直し」であり、対象との対話、他者との対話、自己との対話によって遂行されている。 |
| 9 |
習熟度別指導の問題点。学力向上の方法として習熟度別指導が導入されているが、習熟度別指導は逆に学力低下と学力格差の拡大を引き起こすというのが、これまでの調査研究の結果から示されている。その原因を理論的に考察する。 |
| 10 |
協同的学びによる学力形成。学力向上の有効な方法として協同的学びが着目されている。なぜ、協同的学びは学力向上にとって有効なのか。その理論的根拠を探り、協同的学びの可能性を提示する。 |
| 11 |
協同的学びによる真正の学び。協同的学びのすべてが学力の向上にとって有効であるわけでない。協同的学びが、高いレベルの学習課題を追求し、教科の本質に即した真正の学びとして展開される必要性を指摘する。 |
| 12 |
質と平等の同時追求。21世紀の教育改革は「質と平等の同時追求」を中心的テーマとしている。この視点から学力問題を再解釈し、学力向上の方法を再検討する。 |
| 13 |
学力の評価と学校政策。学力テストによるアカウンタビリティ政策は、官僚主義と競争主義の学校政策を導く危険がある。学力評価を官僚主義と競争主義に陥らせないための要件について討議する。 |
| 14 |
改革の展望。学力の向上は、学びの経験の質の向上と学びにおける平等を実現することによって達成できる。この原理に立って、学力問題をめぐる学校改革の展望について討議する。 |
| 15 |
理解度の確認。授業の全体をとおして総括的な理解度を確認する。 |