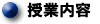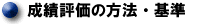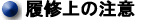| 1 |
オリエンテーション 「手で書くことの意義」について |
| 2 |
行書の特徴について 行書の成立 |
| 3 |
行書の基本点画と鑑賞(1) 点画の曲線化 |
| 4 |
行書の基本点画と鑑賞(2) 点画の変化(収筆・トメ・ハネ・払い) |
| 5 |
行書の基本点画と鑑賞(3) 点画の変化(方向・長さ) |
| 6 |
行書の基本点画と鑑賞(4) 点画の連続(筆脈・実画、虚画) |
| 7 |
行書の基本点画と鑑賞(5) 点画の省略、筆順の違い、概形と文字の中心 |
| 8 |
行書の古典鑑賞と臨書(1) 書風について考える(重厚な行書) |
| 9 |
行書の古典鑑賞と臨書(2) 書風について考える(軽快な行書) |
| 10 |
行書の古典鑑賞と臨書(3) 様式に対応した構成法(臨書から創作へ) |
| 11 |
行書による創作と鑑賞(1) 半紙(古典集字による倣書) |
| 12 |
行書による創作と鑑賞(2) 画箋紙半折(1/2〜1/3) |
| 13 |
行書による創作と鑑賞(3) 画箋紙半折 |
| 14 |
行書のまとめ 「私の好きな行書」レポート提出 |
| 15 |
草書の特徴について 草書の成立 |
| 16 |
草書の基本点画と用筆・運筆法(1) |
| 17 |
草書の基本点画と用筆・運筆法(2) |
| 18 |
草書の古典鑑賞と臨書(1) 書風について考える(率意の書など) |
| 19 |
草書の古典鑑賞と臨書(2) 書風について考える(書譜) |
| 20 |
草書の古典鑑賞と臨書(3) 書風について考える(自叙帖) |
| 21 |
草書の古典鑑賞と臨書(4) 書風について考える(顔真卿の書) |
| 22 |
草書の古典鑑賞と臨書(5) 様式に対応した構成法(創作の手順・方法) |
| 23 |
草書による創作と鑑賞(1) 半紙(古典集字による倣書) |
| 24 |
草書による創作と鑑賞(2) 画箋紙(1/2〜1/3) |
| 25 |
草書による創作と鑑賞(3) 半折 |
| 26 |
行書と草書による創作・鑑賞(1) (半紙) |
| 27 |
行書と草書による創作・鑑賞(2) (色紙、扇面など) |
| 28 |
行書と草書による創作・鑑賞(3) (半折)/レポート及び作品綴提出 |
| 29 |
草書のまとめ 「私の好きな草書」レポート提出 |
| 30 |
総括 レポート及び作品綴を返却 |