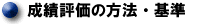| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 第1学期 小松 大秀 講師 第2学期 田辺 龍太 講師 |
3 | 4 | 通年 | 水 | 2 |

 もの"を次世代につなぐ使命を理解し、実際の展示施設ではどのように仕事がおこなわれているかを、具体的に学ぶことで、展覧会を「見る側」に立っている履修生が、実習を経て「見せる側」の視点を確立すること、博物館・美術館で、学芸員として働くうえで必要な基礎を、実践的に習得することを目的とする。
もの"を次世代につなぐ使命を理解し、実際の展示施設ではどのように仕事がおこなわれているかを、具体的に学ぶことで、展覧会を「見る側」に立っている履修生が、実習を経て「見せる側」の視点を確立すること、博物館・美術館で、学芸員として働くうえで必要な基礎を、実践的に習得することを目的とする。
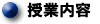
| 1 | オリエンテーション(第1学期ガイダンス) |
| 2 | もしも博物館に勤めたら① 博物館の存在意義、わが国における博物館の成り立ち |
| 3 | もしも博物館に勤めたら② 博物館における日常業務の内容 |
| 4 | もしも博物館に勤めたら③ 博物館に勤務する研究員に求められる資質 |
| 5 | もしも博物館に勤めたら④ 博物館に勤務する研究員に求められる技術 |
| 6 | 見学実習の準備 東京国立博物館見学に向けて、同館の成り立ち、特色、展示コンセプトを知る |
| 7 | 見学実習① 東京国立博物館見学 展示方法などについて学ぶ |
| 8 | 取扱実習の準備 作品を取り扱う際のマナー、注意事項について |
| 9 | 作品取扱① 彫刻作品について実際の取扱、梱包をおこなう |
| 10 | 作品取扱② 絵画作品のうちの掛軸について保存箱から取り出し、取扱、収納をおこなう |
| 11 | 作品取扱③ 絵画作品のうちの絵巻などの巻子本について開帳、収納をおこなう |
| 12 | 作品取扱④ 絵画作品のうちの屏風について保存箱から取り出し、開帳、収納をおこなう |
| 13 | 作品取扱⑤ 工芸作品のうちの陶磁器について保存箱から取り出し、収納をおこなう |
| 14 | 作品取扱⑥ 工芸作品のうちの漆芸品と金工品について保存箱から取り出し、収納をおこなう |
| 15 | ディスカッションを通じて、第1学期のまとめをする |
| 16 | オリエンテーション(第2学期ガイダンス) |
| 17 | 博物館・美術館の現実を考える |
| 18 |  もの"の収集と管理 実際の収集品について、その収集の理念やコンセプトを探る もの"の収集と管理 実際の収集品について、その収集の理念やコンセプトを探る |
| 19 |  もの"の保存と活用 実際の収集品を確認、比較し、保存や活用につなげる方法を学ぶ もの"の保存と活用 実際の収集品を確認、比較し、保存や活用につなげる方法を学ぶ |
| 20 |  もの"の整理と研究 もの"の整理と研究  もの"から知ったこと(整理と研究=情報)を相手に伝えることに取り組む もの"から知ったこと(整理と研究=情報)を相手に伝えることに取り組む |
| 21 | 見学実習② 東京国立博物館見学 研究員の学術的成果が展示、講演会、教育普及に反映されることを知る |
| 22 | 企画立案とイベントの実状① イベントとは 何らかの目的を達成するための手段"として開く行事・催事と認識する 何らかの目的を達成するための手段"として開く行事・催事と認識する |
| 23 | 企画立案とイベントの実状② 小グループに分かれての実践(複数で意見交換しながら企画を構築する) |
| 24 | 企画立案とイベントの実状③ 小グループに分かれての実践(来館者へのサービスとリピーター獲得の施策を考える) |
| 25 | 企画立案とイベントの実状④ 小グループに分かれての実践(他機関、地域との連携を考える) |
| 26 | 企画立案とイベントの実状⑤ 小グループに分かれての実践(マスコミへのPR戦略を練り、スタッフ間での情報を共有する) |
| 27 | 企画立案とイベントの実状⑥ 学習院大学敷地内の特徴的な場所を選び、模擬のギャラリートークを実施する |
| 28 | 各種刊行物を手に取り、良い点と改善点を討論する |
| 29 | 見学実習③ 切手の博物館見学 小規模館の展示以外での工夫を探る |
| 30 | 第2学期のまとめ 博物館・美術館の観衆に向けての信頼性、コミュニケーション能力の重要性を再認識する |
| 第1学期の授業は小松大秀講師が担当し、第2学期の授業は田辺龍太講師が担当する。 |

 もの"や
もの"や 他者"との直接的な交流が必要であることを、実体験や実技を通して習得する。
他者"との直接的な交流が必要であることを、実体験や実技を通して習得する。