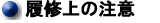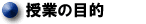
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 家永 遵嗣 教授 | 2 | 1 | 通年 | 水 | 2 |
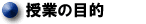
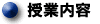
| 1 | 第1学期 授業の進め方について説明し、テキストを配布・確認し、発表当番を決めます。 |
| 2 | 近江国菅浦という惣村について、現状のスライドをまじえつつ、地理的・歴史的な環境・特徴を説明します。 |
| 3 | 『菅浦文書』628号「菅浦惣庄合戦注記」(文安六(1449)年二月十三日)と『同』323号「菅浦・大浦両庄騒動記」を輪読します。適宜、藤木久志「武装する村」・「刀狩りをみる目」の関連部分を読み、論文の要旨をまとめる課題を課します。 |
| 4 | 〃 |
| 5 | 〃 |
| 6 | 〃 |
| 7 | 〃 |
| 8 | 〃 |
| 9 | 〃 |
| 10 | 〃 |
| 11 | 〃 |
| 12 | 〃 |
| 13 | 〃 |
| 14 | 〃 |
| 15 | 〃 |
| 16 | 課題論文の分担を決め、論点をレクチュアします。 |
| 17 | 分担に沿って発表討論します。(17~30回) |
| 当番を決めて史料を読み討論する「講読」の要領と、論文を読み解いて論議する「研究発表」の要領を体験します。使用する菅浦の史料は漢文の記述法が混じっていますが、基本的に仮名の和文です。中世のムラの指導者たちがムラの住民たちに読み聞かせたもので、かれらの世界を生き生きと伝えてくれるものです。第2学期の課題論文は、グループで分担して発表討論します。 |