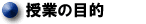
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 平田 栄一朗 講師 | 2 | 1~4 | 第2学期 | 金 | 4 |
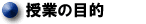
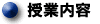
| 1 | イントロダクション:メランコリーの特徴・歴史的変遷について |
| 2 | レペニース著『メランコリーと社会』を参照にしつつ、社会とメランコリーの関連性を歴史的にたどる(1) |
| 3 | レペニース著『メランコリーと社会』を参照にしつつ、社会とメランコリーの関連性を歴史的にたどる(2) |
| 4 | 社会とメランコリーの歴史的変遷(20世紀を中心) |
| 5 | ルネサンスのメランコリー:デューラーの「メランコリアⅠ」を手掛かりにして |
| 6 | 宗教改革とバロック時代のメランコリー:ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』を手掛かりにして |
| 7 | 廃墟とメランコリー |
| 8 | 現代のメランコリー:アラン・エランベールの論を中心に |
| 9 | 女性のメランコリー:ジュリア・クリステヴァの『黒い太陽』 |
| 10 | メランコリーと現代演劇(1) |
| 11 | メランコリーと現代演劇(2) |
| 12 | 日本文学とメランコリー(1) |
| 13 | 日本文学とメランコリー(2) |
| 14 | 授業のまとめ |
| 15 | 自主研究 |
| 16 | オリエンテーション(1):演劇性の基本的な考え方:ゴフマン の理論、模倣論、遊戯論、儀式論、主体の演劇性、メディア・リプ レゼンテーションとの関係などについて紹介します。 |
| 17 | オリエンテーション(2):演劇性の基本的な考え方:ゴフマン の理論、模倣論、遊戯論、儀式論、主体の演劇性、メディア・リプ レゼンテーションとの関係などについて紹介します。 |
| 18 | オリエンテーション(3):演劇性の基本的な考え方:ゴフマン の理論、模倣論、遊戯論、儀式論、主体の演劇性、メディア・リプ レゼンテーションとの関係などについて紹介します。 |
| 19 | 自己演出:精神分析のモデルとして |
| 20 | 権力の演出 |
| 21 | スタイルと文化の演出(1) |
| 22 | スタイルと文化の演出(2) |
| 23 | 都市の演劇性・演出(1) |
| 24 | 都市の演劇性・演出(2) |
| 25 | スペクタクル社会の演劇性(1) |
| 26 | スペクタクル社会の演劇性(2) |
| 27 | 儀式性と演劇性 |
| 28 | ジェンダーの演劇性 |
| 29 | 授業のまとめ |
| 30 | 自主研究 |



