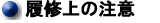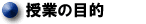
| 担 当 者 | 単 位 数 | 配当年次 | 学 期 | 曜 日 | 時 限 |
| 安原 伸一朗 講師 | 4 | 3~4 | 通年 | 火 | 2 |
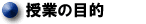
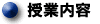
| 1 | イントロダクション |
| 2 | 証言の可能性と不可能性:プリーモ・レーヴィ |
| 3 | 「証言作品」の意義:ピエール=ヴィダル・ナケ |
| 4 | 今日、極限体験を語ることの意味:ケルテース・イムレ |
| 5 | 「人類」であること:ロベール・アンテルム |
| 6 | 映画鑑賞 |
| 7 | 収容所の世界I:ダヴィッド・ルーセ |
| 8 | 収容所の世界II:エリ・ヴィーゼル |
| 9 | 収容所の世界III:シュロモ・ヴェネチア |
| 10 | 女性の収容所I:シャルロット・デルボ |
| 11 | 女性の収容所II:ミシュリーヌ・モーレル |
| 12 | ヴェルディヴ事件:ガブリエル・ヴァックマン |
| 13 | 戦後の混乱:マルガレーテ・ブーバー=ノイマン |
| 14 | 極限体験を語ることの危険と必要性:アラン・パロー |
| 15 | レポートの課題説明 |
| 16 | 極限体験と自己検閲:アンヌ=リーズ・ステルン |
| 17 | 「ことば」のステイタスI:ディオニス・マスコロ宛のロベール・アンテルムの書簡 |
| 18 | 「ことば」のステイタスII:ジャン・ケロール |
| 19 | 「ことば」のステイタスIII:ホルヘ・センプルン |
| 20 | 「ことば」のステイタスIV:モーリス・ブランショ |
| 21 | 「ことば」のステイタスV:クロード・ムシャール |
| 22 | 「ことば」のステイタスVI:ピエール・パシェ |
| 23 | 映画鑑賞 |
| 24 | 収容所における「芸術」I:シモン・ラックス |
| 25 | 収容所における「芸術」II:プリーモ・レーヴィ |
| 26 | 収容所とその後I:ケルテース・イムレ |
| 27 | 収容所とその後II:ジョルジュ・ペレック |
| 28 | 収容所とその後III:アンリ・ラクシモヴ |
| 29 | 収容所の「可能性」:ジョルジュ・バタイユ |
| 30 | レポートの課題説明 |
| 主として「証言作品」として考えられる作品の抜粋を読解し、背景の解説を織り交ぜていく。また、「証言作品」にかかわる研究書や、「証言作品」に影響を受けている文学作品なども随時、読んでいく予定。なお、読んでいく作品はフランス語圏のものに限らないが、フランス語訳を用いる。 |